価値観の違いで離婚した元夫…。ありがたいことに、離婚して10年経っても、しっかり養育費を支払い続けてくれている。
でも少し不安になることがある…。もしも夫が再婚したら、万が一死んじゃったら…。養育費はどうなるの?
そもそも養育費とは?~誰が貰える権利なの…?~

子どものいる夫婦が離婚した場合、親権(もしくは監護権)を持っていない方は。養育費を支払うことになります。すこし勘違いしがちですが、養育費を貰う権利は親権者(もしくは監護者)にあるのではなく、その子供にあります。子どもが未成年であるため、代理して親権者がその権利を行使しているにすぎません。離婚しても、子どもとの親子関係がなくなるわけではないので、当然非親権者は養育費を支払う義務が発生します。
とはいえ、日本における養育費の支払い率は低く、およそ全体の3割です。かなり低い数値ですね…。
世界的に見ても、日本の養育費制度には欠陥がある?~それでも改善のきざしが…~
欧米諸国では、養育費をあらかじめ給料天引きにしたり、国の立て替え制度を確立させているところが多いです。対して日本は、強制執行文言付き公正証書を作成しないと、給料の差し押さえをすることが出来ません。欧米諸国とは、親権や離婚のシステムが異なるので、一概には言えませんが、整備が遅れていることは否めないでしょう。
とはいえ、2019年に12月に裁判所が公開している、「養育費算定表」が改定。上方修正されました。
また、兵庫県の明石市では、不払いの養育費の催促や立て替えを自治体がサポートしてくれる制度が始まりました。
明石市にお住まいの方で困っている方は、明石市のホームページをご確認ください。
また、東京の豊島区や千葉市といった、他の自治体でも養育費安心サポートなどの民間事業の利用を助成してくれるところもあります。加えて、養育費の相談を受け付けているところもあります。不払いの心配があるときには、まず自治体に相談のうえ、民間の養育費事業の利用を検討してみても良いかもしれませんね。
 【養育費について考えてみよう】養育費の基本知識
【養育費について考えてみよう】養育費の基本知識
夫が再婚したら養育費の支払いは無くなる?

前章では、養育費を貰う権利や、日本の養育費の現状について確認してきました。本章では、元夫が再婚した場合、今まで支払われていた養育費が支払われるのか、について確認していきたいと思います。
シングルマザーは養育費を必要としている…!
2016年に厚生労働省が公表した、「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」によると、シングルマザーの年収は、243万円でした。育児に時間があてられるため、なかなか思うように仕事が出来ず、シングルマザー世帯のおよそ51.4パーセントは貧困状態(※)にあるとされています。
そのため、非親権者である元夫からの養育費はとっても大事な収入なのです。
※第5回子育て世帯全国調査(2018)参考
元夫が再婚したら養育費を支払ってもらえない?
離婚理由によって、さまざま思うところがあると思いますが、心配になるのは養育費です。
新しい家族が出来たら、養育費の減額や免除になるのかと言えば、ケースバイケースです。
養育費の免除については、ほとんど認められていないといっても良いです。たとえ、借金を抱え自己破産したとしても、養育費の滞納や支払いは、免除の対象ではありません。
そのため、夫が再婚をしたとして、減額はあっても免除はないと考えてよいと思います。(再婚にかこつけて不払いになってしまう可能性は否めませんが…)
なお、再婚して減額認められるケースは、再婚した女性とのあいだに子どもが出来たり、女性の連れ子と養子縁組をしたときなどです。
養育費の減額の手順ってあるの?
養育費の減額の方法については以下のような段階があります。
- 夫婦で話し合って、減額を決める
- 家庭裁判所で養育費の減額調停を申し立てる
夫婦で話し合って、減額を決める
元夫と話し合って決められれば、一番ですね。元夫から状況を確認し、どれくらい減額を決めるかすり合わせをおこなうといいと思います。
話合いでは、まず相手の事情を聞き、こちらの収入状況などを正確に伝えた方が良いです。「養育費を据え置きにしないと、面会させない」とか、「不幸になってほしいのに再婚したのが許せないから、減額には応じない」といった、感情的な理由を述べると、関係がこじれかねないので注意しましょう。
なお、離婚時に養育費の取り決めを公正証書にした場合は、新しい内容で公正証書の再作成が必要になることもあります。
家庭裁判所で養育費の減額調停を申し立てる
夫婦同士の意思疎通がうまくいかないときには、元夫から養育費の減額調停を申し立てられる可能性があります。減額の可否の焦点は、以下のとおりです。
- 非親権者(非監護者)の収入が減った
- 親権者(監護者)の収入が増えた
- 非親権者が、再婚して扶養家族が増えた
相手方はおそらく上記のいずれかを焦点にして、減額を求めてくると思います。調停を申し立てられたときには、冷静に対応することが大切です。調停の申立人が、調停で有利になるということはありません。建設的に、論理的に自分の主張を組み立てて、養育費の減額幅を出来るだけ抑えるようにすると良いでしょう。
妻側が再婚したら、夫の養育費の支払い義務はチャラに…?

前章では、元夫が再婚した場合について考えました。本章では、反対にあなた自身が再婚を決めたときの養育費の支払いについて考えていきましょう。
離婚したひとの再婚率
2016年に厚生労働省から発表された、「婚姻に関する統計」によると、離婚した女性の再婚率は、16.8%です。つまり、10人に1人以上は再婚しているという結果になりますね。
シングルマザーの方も子どもとの関係、元夫とのトラブルなど、ひとによってハードルはありますが、再婚を選択している方もいます。世の中には魅力的な男性がたくさんいるので、再婚するのもうなずけますよね。
とはいえ、気になるのは再婚した場合の養育費について。再婚しても引き続き養育費は貰えるのでしょうか。
再婚しても、原則として養育費は貰える!~けど、新しい夫の収入によっては減額も~
基本的に、あなた自身が新しいひとと再婚をしたとしても、元夫の養育費の支払い義務は消えません。法律上の父親、である限りは養育費を支払い続ける義務があります。
また、法律的には元夫への再婚報告は、義務ではありません。とはいえ、公正証書で再婚報告の取り決めをおこなっていたケースでは、しっかり報告をおこなった方が良いでしょう。そのうえで、元夫から養育費の減額の申し出があった場合には、話し合いに応じることが大切です。
なお、離婚後、なにか事情があった場合、養育費減額調停を申し立てられるケースがあります。このような場合、再婚を報告していなかったり、調停委員に話したことと、元夫に説明したことに食い違いがあると、裁判官(調停官)や調停委員からの心証が悪くなることもあります。心証が悪いと、養育費の大幅な減額や打ち切りになることもあるので注意しましょう。
知っておきたい、養子縁組のこと
再婚をして、新しい夫と夫婦になっても、元夫との子どもが自動的に新しい夫の法律上の子どもになるわけではありません。普通養子縁組、特別養子縁組といった手続きを経て、法律上の親子関係になります。
普通養子縁組と特別養子縁組の違いを以下にまとめてみましたのでご確認ください。
普通養子縁組と特別養子縁組の違い
| 養子縁組の種類 | 普通養子縁組 | 特別養子縁組 |
| 養子縁組が認められるおもな要件 | 養い親が成年である、もしくは結婚歴があること
養子が養い親よりも年上でないこと 養い親が養い親になるという意思があること 15歳未満の場合、養子になることを法定代理人(親権者)に許可を得ること
|
養い親のひとりが25歳以上で、もう一方が20歳以上であること
原則として養子が15歳未満であること(例外15歳から17歳) 原則として実の両親に同意を得ていること 特別養子縁組を請求して6か月間の監護状況をみて、裁判所が成立させることがふさわしいと判断したとき 実父母の監護が著しく困難、もしくは不適当だと判断されたとき |
| 特徴 | 養い親、実親ともに親子関係が認められる | 実親との親子関係が完全になくなる |
| 申立先 | 家庭裁判所(養子になる対象が未成年の場合) | 家庭裁判所にて審判で判断 |
| 届出先 | お住まいの市区町村の役所の窓口。2人以上の証人が必要。 | 審判がくだってから、10日以内にお住まいの市区町村の役所に提出 |
特別養子縁組は、法律上、実親との完全に断ち切りますので、必ず家庭裁判所をとおし、審判をおこなう必要があります。特別養子縁組は、子どもを育てられない家庭から、別の家庭に迎え入れる制度なので、再婚して連れ子の場合に認められることは、滅多にありません。
したがって、よく利用されるのは普通養子縁組の方になります。
普通養子縁組を組むと、実の親(元夫)・養い親(この場合は、新しい夫のことです)、両方と親子関係が結ばれることになります。つまり、普通養子縁組を組んでも、法律上、元夫と子どもの親子関係が切れるわけではないので、養育費の義務は原則として継続されます。
ただし、養い親(新しい夫)の収入状況によっては、養育費の減額が認められることもあるのです。
万が一、元夫が死亡した場合の養育費と相続のアレコレ

離婚と相続。一見、全然関わり合いのないように見えますが、元夫が若くして亡くなってしまった場合、子どもに相続権が発生します。「元夫が再婚しても子供に相続権は発生するの?」「元配偶者には相続権はないの?」と色々疑問を持つ方もいらっしゃると思いますので、簡単に相続権について解説していきたいと思います。
相続の大前提!~相続権を持つことのできるひと!~
| 相続の権利を持てる人と優先順位 | 関係性 |
| 絶対相続人になれる | 配偶者(夫、もしくは妻) |
| 相続順位1位 | 子ども(子供が死亡している場合は、孫) |
| 相続順位2位 | 両親(両親が死亡している場合は、祖父母) |
| 相続順位3位 | 兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合は、甥や姪) |
※簡略化しております。相続順位に関して詳細を確認されたい方は、国税庁の「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」をご確認ください。
相続順位…といっても、耳慣れない言葉ですよね。分かりにくいと思いますので、以下の例を参考にしてみてください。
相続権を持てるのは、元妻とのあいだの子どもです。元配偶者である元妻には、相続権は発生しません。ただし、こどもが未成年だった場合、法定代理人として遺産の話し合い(遺産分割協議)に参加することになります。なお、相続する意思が無く、相続放棄をした場合には、相続順位2位の夫の両親に相続権が移ることになります。
相続権を持てるのは、再婚相手である現配偶者と、再婚相手の連れ子を含めた子ども4人です。元妻には、相続権はありません。ただし、2人の子どもが未成年だったときは、法定代理人として遺産の話し合い(遺産分割協議)に参加することになります。
連れ子は、元夫と、養子縁組をしています。民法では、
すので、血のつながりはなくとも相続権を持つことが出来ます。
元夫が万が一亡くなってしまった場合、子どもが相続権を持つことになります。離婚の理由によっては、再婚相手や、元夫の両親と相続トラブルになる可能性が大いに有り得ます。加えて、通常の相続よりも手続きが煩雑になる可能性も否めませんので、弁護士に相談して見てもいいかもしれませんね。
元夫が死亡した場合、誰かが代わりに養育費払ってくれるの?
養育費の支払い義務は、一身専属権です。一身専属とは、特定のひとのみが持つことが出来る権利で、誰かに引き継がれることはありません。そのため、元夫が死亡した後からの養育費を元夫の家族に請求することは出来ないのです。
ただし、過去、養育費に未払いがときには話は別です。過去に発生していた養育費は請求することが出来ます。
以上が、元夫が死亡した場合の相続や養育費についての解説でした。
 【離婚後のトラブル】元夫が亡くなった!元妻が行うべきことはあるの?
【離婚後のトラブル】元夫が亡くなった!元妻が行うべきことはあるの?
まとめ

今回は、離婚後の養育費のトラブルについて確認していきました。再婚に、死亡。どちらも、離婚した時点ではわからないことなので、いざ直面するとどうしたらいいかわからなくなってしまうと思います。
しかし、わからないまま放置していると、養育費が不払いになったり、勝手に減額されたりということが発生するかもしれません。予想だにしないトラブルが起こった場合には、弁護士に相談することを検討した方が良いかもしれません。事務所によっては初回無料のところもありますので、一度確認してみてはいかがでしょうか。
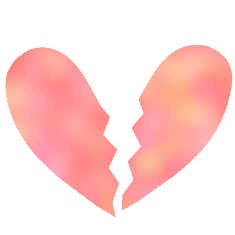 りこんの窓口
りこんの窓口



コメントを残す