悪気が無いのはわかってる。でもさ、やっぱ許せんのだわ!
娘が生まれて退院して、すぐ言われた言葉。
「明日友達とキャンプ行ってくるわ!」じゃねーよ!!!
夫の気遣いはまじで、おかどちがい。もう1年我慢してるんだけど、もう無理。
無理寄りの無理!でも、こんなことで離婚って…私に堪え性がないの?
産後クライシス~地味にむかつく夫の発言~

子どもを妊娠することは女性しかできません。妊娠と出産は、女性に与えられた試練であり、また喜びでもあるでしょう。自分のなかに、ひとつの命が育っていき、痛みを乗り越えて出産する。
言葉でいうのは簡単ですが、めっちゃくちゃ大変です。赤ちゃんを産む前もですが、産んだ後もなかなか、体力は戻りません。
出産後、出産前の身体に戻るまでの期間を、産褥期と言います。産褥期は、個人差もありますが、大体6週間から8週間と言われています。
初めての授乳でおっぱいは痛いし、子宮は大けが状態で、血が出る。そんな中でも赤ちゃんは待ってくれないので、育児をしなければいけません。
この気持ち、全然理解してくれない夫といると、イライラを通り越して哀しくなってしまいますよね。
実際、出産後、夫婦仲が急激に悪くなることは、多く起こりえると言われています。いわゆる、産後ブルーや産後クライシスと呼ばれるものです。
離婚の時期は末子年齢が0~2歳であることが多い!
産後クライシスとは子どもの生後半年以内に起こることが多いです。出産を経験した女性の7割近くが、産後クライシスを経験しているという説もあります。
また、少し古いデータですが、厚生労働省が平成28年におこなった、「全国ひとり親世帯等調査結果」によると、離婚してシングルマザーになったおよそ、39.6パーセントが、末子年齢(※)0歳~2歳でシングルマザーになったと回答しています。
つまり、4割近くの女性が、子どもが小さいうちに離婚しているのです。他の分布も気になる方がいると思いますので、詳細は下記のグラフをご確認ください。
※末子年齢…末っ子の年齢のことです。
全国ひとり親世帯等調査結果 母子世帯になったときの末子年齢(生別)を参考

グラフの分布を確認すると、末子年齢が低いときに離婚する傾向にあり、12歳以降は割と低めな数値となっています。
このことから、育児が一番大変な時期に、夫に協力してもらえず、離婚をする方が多いのではないかと推論が立てられそうです。
育児が大変な時期の発言は後を引くので、離婚回避するためには夫に伝えてみよう
- 言ってくれればやったのに
- 飲み会行ってくるから
- 俺は仕事してるし、育児はお前の仕事だろ
- 育児なんて簡単でしょ?
- 俺の母さんは一人でやってたよ
上記のような言葉を夫に言われたことありませんか。相手は悪意なく言っているのかもしれませんが、言われた方は…。
特に、夫の母親(義母)と比べられるのは、非常に腹立たしい気分になると思います。「あんたの母親のことは聞いてねーよ」とつい、暴言吐きたくなりますよね。
出産後はホルモンバランスが崩れがちで、少しのことでイラついてしまいます。夫の気遣いの方向性が違うと余計フラストレーションがたまってしまうこともあるのです。
とはいえ、夫婦であってもお互いの考えをすべて理解できるわけではありません。口で言うとつい、感情が高ぶってしまう傾向にあると思います。そこでLINEや手紙などを使い、「○○をやってくれてるのは助かっている」と、日常的に夫が協力してくれていることがあれば、そのことに対し感謝したうえで、夫にやってほしいことを伝えてみてはいかがでしょう。
そうすることによって、夫婦の意思疎通がとれ、関係が改善するかもしれません。
 【離婚の知識】離婚を意識したときに知っておくべき法律用語を解説
【離婚の知識】離婚を意識したときに知っておくべき法律用語を解説
イクメンと自称するけど何もやらない夫との離婚は可能か
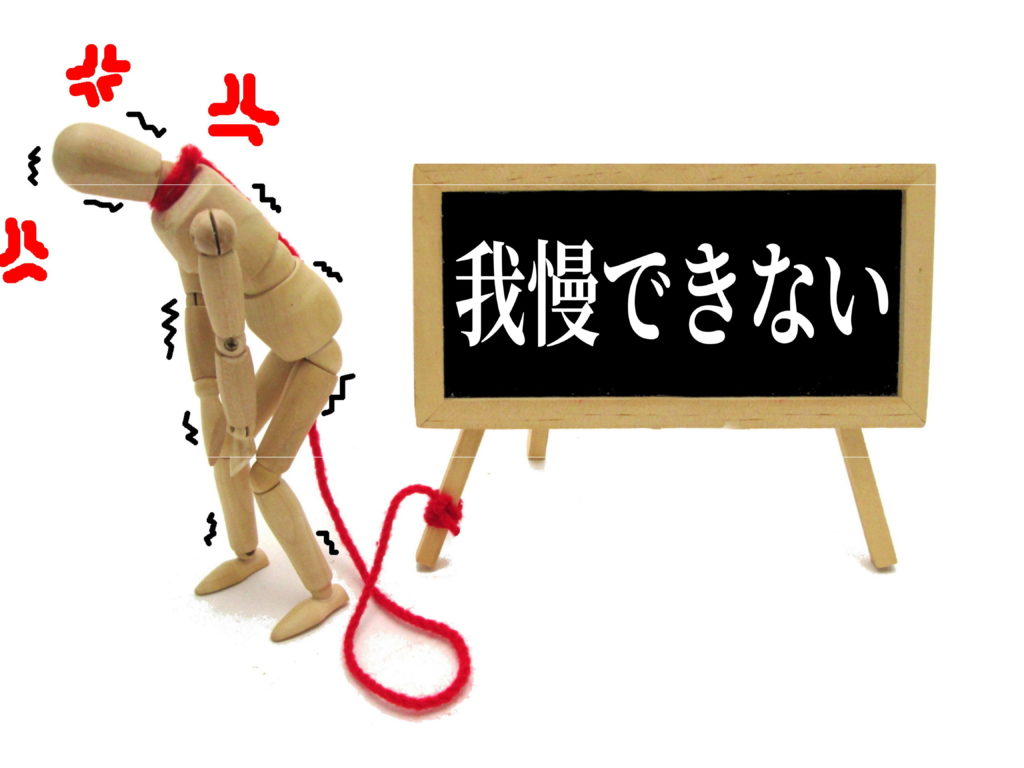
夫婦内で起こりがちなトラブルとして、現状の認識の齟齬が挙げられます。哀しいことですが、認識の齟齬によって、「夫を心底に嫌いになった」という話をよく耳にすることがあります。
日本では、明治期にはいったくらいから、「育児」や「家事」などは、女性の仕事として考えられました。平成、令和と時代が下るにつれ、「男性の育児参加」の認知が進んできていますが、なかなか固定観念は取り払えないようです。
夫の育児参加率を高めようと、厚生労働省では、2010年6月から「イクメンプロジェクト」を始めました。
これは、男性の育児参加をうながすとともに、育児休暇率を2020年までに13パーセントを目指すというプロジェクトです。
2010年度は1.38パーセントだったのが、2019年度には7.48パーセントと大幅にポイントは上がりましたが、目標値の13パーセントには届きそうにないのが現状です。
育児をしない夫との離婚は可能か
離婚は、大きく分けて3段階に分けることが出来、以下のようになります。
- 協議離婚
- 調停離婚
- 裁判離婚
上記のうち、協議離婚や調停離婚については、話し合いで解決を目指す方法なので、「夫が育児をしない」と言う理由で離婚することも可能です。ただし、裁判までもつれこんでしまうと、相手方の行動が法定離婚事由に当てはまらなければなりません。
すでにほかの記事でも何度か紹介しておりますので、ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、念のため、以下に記載させていただきますね。
【法定離婚事由】
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上生死不明
- 配偶者が強度の精神病で回復を見込めない場合
- その他婚姻を継続し難い重大な事由
「夫が育児に協力しない」は1~5のどれに当てはまるのでしょう。
夫が育児に協力しないことは、5の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。ただし、法定離婚事由に当てはまるためには、それが原因で夫婦関係が破綻したという証明が必要になります。
したがって、実際的には育児に非協力的のみですと、法定離婚事由に当てはまらない確率の方が高いです。
離婚したいなら、まずは協議、もしくは調停の利用を検討する
裁判での離婚は、最終手段で、どんな理由でも誰でも利用できるという制度ではありません。そのため、まずは夫婦間の話し合いである離婚協議からはじめると良いでしょう。
先ほど紹介した離婚協議と離婚調停の大きな違いは、家庭裁判所に申し立てるかどうかの違いです。
離婚協議は夫婦間でおこなう話し合いで、特に申請は必要ありません。対して離婚調停は、家庭裁判所に「夫婦関係調整調停(離婚)」を申し立てる必要があります。
育児に非協力的な夫には、ついつい感情が先立ってしまい、話し合いが進まない恐れがあります。したがって、何回か夫婦間で話し合い、「折り合いがつかない」「冷静に話し合えない」と感じた時には、調停を申し立てることをおすすめします。
なお、離婚調停では離婚の可否のほか、共同財産や養育費についても話し合うことが可能です。
調停で離婚が成立した場合、調停証書という書類を入手することが出来ます。調停証書は、養育費についての取り決めをしていると、離婚後養育費の支払いが滞った場合、法的に強い効力を持ちます。
給料差し押さえなどの強制執行も可能なので、離婚の可否以外で、もつれそうなことがある時には調停の申し立てを検討しても良いかもしれません。
体験談

これまで育児や家事に非協力的な夫についてさまざまな観点から考えていきました。本章では、夫の勝手な行動に我慢ならず、離婚した妻の体験談についてご紹介したいと思います。
【離婚を決めた】君は口だけ、何もやらない夫
夫:ひろき(38)
妻:まいこ(34)
娘:なこ(1)
娘のなこが生まれたのは、私がひろきと結婚して7年目のときでした。なかなか子宝に恵まれず、1年間の妊活の末、生まれた子どもでした。
念願の子だったので、夫婦そろって大喜び。「これから、大変なこともあるだろうけれど、一緒に頑張ろう」とふたりで約束を交わしました。今思えば、このときが一番幸せだったのかもしれません。
出産後、なかなか体力が戻らず3週間ほどの入院を経て、なこを連れ、家に戻りました。すると家の中はぐちゃぐちゃ。ゴミ袋がいくつかたまっており、流しにも洗っていない食器がたまっていました。おまけに、窓はずっと締め切ったのでしょう。空気が悪く、部屋の中もワイシャツやらネクタイやらが散らばっていました。
元々家のことはあまりやらないひとでしたが、3週間でこんなに汚くなるなんて思いもしませんでした。これは、今後良くないということで、彼に、家事と育児を頑張るつもりだが、今まで通りにはならないことを伝え、これからは家のことに協力してほしいと伝えました。
すると、夫はふたつ返事で了承したので、部屋を汚くしたことには文句を言わず、しゅくしゅくと片づけました。
それから1週間ほどは、夫も彼なりに家事を頑張ってくれました。しかし、長くは続かず…。次第に、私に育児と家事の比重が大きくなりました。なこは夜泣きがひどく、慢性的に寝不足状態だった私は、彼に「家事やるって約束したじゃん」と強めな口調で言いました。
すると、まずいと思ったのだろう夫は、すぐさま謝ってきました。一応の謝罪を受け入れ、今後は家事を手伝ってくれることを再度約束しました。
しかし、舌の根も乾かぬうちに、「明日、飲み会行ってくるから」と。彼には父親の自覚が無いのでしょうか。
そこでまたケンカをしましたが、彼は結局飲み会に参加しました。なこが生まれてまだ1か月くらいのことでした。
その後も、夫の行動は改善せず、なこの機嫌のよいときだけを狙って、かわいがるばかりでした。子どもはかわいいだけでは育ちません。
それなのに、おむつも変えない、ミルクも上げられない、お風呂も入れない。掃除洗濯、食事の用意も手伝わない。
「こいつと一緒にいない方が快適なんじゃないだろうか」と思ってしまいました。
決定的だったのは、今年の3月の出来事です。世の中が、コロナの脅威を感知しはじめ、自粛にむけた行動をしていた時に彼は、「友達連れてきた☆」のノリで、自分の友人を連れてきました。
当時は、コロナが未知の病気であったので、「なこに万が一のことがあったら大変だから、悪いけど帰ってもらって」と伝えました。しかし、彼には危機感が無いようで、「大丈夫」としかいいません。
多分、それが決定的な出来事だったんだと思います。今まで、離婚なんて考えてもいませんでしたが、育児も家事もしない、おまけに危機感がまるでない男とは一緒にはいられないと感じました。
そこで、まずは近所に住む両親に連絡し、事の次第を伝え、実家においてもらえるよう説得しました。
はじめは、「たかだか、育児や家事くらいで」と言っていた両親でしたが、私の決意が固いのを察したのか、同居を了承してくれました。
同居の了承が取れたので、夫に離婚を切り出しました。寝耳に水だったのか、彼は「子どもと離れるのは考えられない」と断固拒否しました。感情的になる奴をしり目に、私は、家事や育児のことや危機感のことなど離婚したい原因を出来るだけ論理的に伝えました。
しかしながら、離婚には納得してくれず、また親権についても意見が食い違いました。
そこで、夫に調停を申し立てると伝え、夫婦関係離婚調停(離婚)を家庭裁判所に申し立てしました。コロナの影響で、なかなか調停が始まりませんでしたが、6月末にようやく初回の調停をすることが出来ました。
私の場合、初回ではまとまらず、2回目で調停が成立しました。その結果、親権は私が持ち、共同財産は折半。養育費は、月々6万円と取り決めをおこないました。また、面会交流については、3か月に1度と設定しました。
今は、実家の両親に手伝ってもらいながら、在宅ワークで働いています。育児に仕事にとなかなか大変な毎日ですが、いつかは親子ふたりで暮らしたいと思っているので、頑張っていきたいと思います。
まとめ

今回は育児や家事に協力してくれない夫との離婚について考えていきました。幼い子どもを育てるのは想像以上に大変なことだと思います。
「家のことはすべて女性がになう」という考えは、今は昔の価値観です。夫が育児や家事に協力してくれないときには、まず育児がどれくらい大変なものなのかを伝えてみると良いと思います。感情的に伝えても、なかなか意図が伝わらないと思いますので、タイムテーブルのようなものを作って、視覚的に訴えてもいいかもしれません。
そうすると、理解を得られるケースもあります。一方で何を言っても改善の余地のない夫は、体験談のまいこさんのようにある程度の下準備をしたうえで、離婚を進めても良いかもしれません。
あわせて、離婚をしたいけれども、どこに相談すればいいかわからないという時には、離婚ナビサポートのような、ヒアリングをし状況にあった専門家を紹介するサービスもあります。また、法テラスのような相談内容に沿って、適切な相談窓口に案内してくれるものもあります。
弁護士などの専門家にいきなり相談するのが怖いと思った方は一度利用を検討してみてはいかがでしょうか。
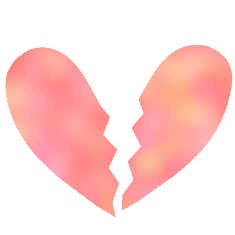 りこんの窓口
りこんの窓口



コメントを残す