夫とはもう〇年も仮面夫婦でいる。このままの状態は、子どもにとっても、私の精神衛生上でもよくない。離婚を切り出したけど、体面を気にして離婚を拒否する。
なんとか離婚したいけど、拒否する夫と離婚なんてできるの。もうどうすればいいかわからない!
この記事でわかること
■離婚拒否できるとき
■離婚拒否ができないとき
■離婚拒否された場合の対処法
相手方に理由が無ければ「離婚」を拒否することが可能
離婚を切り出したとき、夫の反応は二つに分かれます。妻の話を聞くか、拒否をするかの二者択一です。話を聞いて、離婚を拒むケースであれば、夫が話し合いのテーブルにのっているので、交渉の余地があるでしょう。
しかしながら、「断固拒否」「話を聞かない」「取り合わない」と言ったケースでは、そもそも夫が妻の話を聞く姿勢を持っていないので、離婚成立までの道筋が見えなくなることでしょう。
夫婦の一方が離婚の話し合いを拒否する場合、どのように対応していけばいいのでしょうか。
離婚の種類から見る夫婦の『合意』
日本の法律では、離婚について大きく3つに分けられることが出来、以下のようになります。
- 協議離婚
- 調停離婚
- 裁判離婚
離婚する夫婦のおよそ9割が1の協議で離婚を成立させています。協議離婚は、基本的に夫婦の合意のうえで離婚が成立します。2の調停に関しても、成立するには、夫婦の合意が必要です。
つまり言い換えていると、訴訟を起こし、裁判所が離婚の可否を判断する、裁判離婚以外は、原則として夫婦の合意が必要になるというわけです。
反対に言えば、協議や調停で離婚する場合、相手方に原因が無い限り、相手方は離婚を拒否することが出来るのです。
夫が離婚拒否をできるケース
前章では、相手方に原因が無い限り、離婚を拒否することが出来るとお伝えしました。本章では、具体的にどういったシチュエーションが考えられるか、確認していきたいと思います。
夫側が離婚を拒否できるケースとしては以下のようなときが考えられます。
- 妻側に離婚の原因があるとき
- 夫側に離婚の原因が無く、納得いっていないとき
1.妻側に離婚の原因があるとき
離婚の原因が妻側、つまり自分自身にある場合には、離婚することが出来ません。
離婚の原因があるひとのことを有責配偶者と言います。具体的な例は、次章で詳しくお話させていただきますが、自身が有責配偶者である場合、離婚の可否を決めることが出来ません。
つまり、離婚の有無は、相手方(夫)の判断にゆだねられるということです。
なお、相手方が拒否しているのにも関わらず、離婚したいからと言って、勝手に離婚届を提出してしまうと犯罪になる可能性があります。
 【美容にうるさい夫】エステや脱毛に浪費する夫と離婚したい
【美容にうるさい夫】エステや脱毛に浪費する夫と離婚したい
2.夫側に離婚の原因が無く、納得いっていないとき
でもお伝えしましたが、双方に離婚原因が無く、夫側が離婚を拒否しているときには、一方的に離婚することが出来ません。
このようなケースは、「性格の不一致」や「価値観の相違」といった理由での離婚したいときにしばしば起こりえます。
妻が夫に対し、不満を覚えていたとして、夫側が必ずしも同じ気持ちを抱いているとは限りません。
このように、双方の認識の齟齬によって、拒否されることがあるのです。
夫が話し合いに応じてくれるのならば、忍耐強く説得するという手段もありますが、早めに離婚を成立させたいときには、第三者を介して話し合いをおこなった方が良いかもしれません。
夫が離婚拒否をできないケース
前章では、夫が離婚拒否できるケースについて詳しく解説させていただきました。本章では、夫が離婚を拒否できない場合について考えていきたいと思います。
夫側が離婚を拒否できないシチュエーションとは、夫側に離婚原因、つまり法定離婚事由があるときです。
法定離婚事由とは、民法770条に定められており、以下のような事由になります。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上生死不明
- 配偶者が強度の精神疾患で、回復が見込めない場合
- その他婚姻を継続し難い重大な事由
離婚拒否において、特筆すべきは、1,2,5の事由になります。早速解説していきたいと思います。
不貞行為をしたとき
不貞行為とは、肉体関係をともなう不倫のことです。夫が不貞行為を行っていた場合、拒否していたとしても、離婚することが可能です。
民法には記載されていませんが、不貞行為として認められるには、以下のような条件があります。
- 配偶者以外の異性と複数回肉体関係を結んでいた
- 性行為に準ずる行為(挿入行為のみでなく、愛撫も含む)
「性行為に準ずる行為」というと、キスやハグに関しても、不貞行為としてカウントしたくなりますが、残念ながらそれらの行為については認められません。
悪意の遺棄
悪意の遺棄とは、夫婦の関係が破綻することを知っていながら、夫婦の義務を果たさないことを指します。夫婦の義務とは、「同居・扶助・協力」のことであり、民法第七百五十二条にも定められています。
悪意の遺棄の具体例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 妻に伝えず、別居する
- 収入がありながら生活費を入れない
- 夫婦の共同生活に全く協力しない
上記のような行動が夫にみられる場合には、悪意の遺棄に相当する可能性があり、相手方が拒否していたとしても、離婚できるケースがあります。
その他婚姻を継続し難い重大な事由
「その他婚姻を継続し難い重大な事由」と言われても、意味が広すぎてなかなか想像がつきづらいかもしれません。よくある例としては、以下のようなものが挙げられます。
- DV行為(身体的・精神的・性的なものすべてを含める)
- 過剰な宗教活動への従事
- 相手方親族との不仲
- 犯罪行為をした
- 借金などの金銭問題
夫が上記のような行為をしていた場合、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に相当し、相手方が拒否していたとしても、離婚することが可能です。
離婚拒否された場合にとるべき行動
夫から離婚拒否をされた場合の対処法として、下記が考えられます。
- 別居する
- 調停を申し立てる
1.別居する
離婚拒否をされた場合、まず別居を考えてみても良いかもしれません。夫婦双方に離婚原因が無く、相手方が離婚を断固拒否しているケースでは、夫の合意を得るほかありません。
そのため、一旦夫から物理的に離れるためにも、別居することも手段のうちです。
別居する上での注意点として、「別居する」ということを夫に必ず伝えること。というのも、特別な事情が無い限り、別居の意思を伝えないと、法定離婚事由である、「悪意の遺棄」に該当するからです。また別居の実績によって離婚を成立させるには相応の時間がかかることを理解しておきましょう。
ケースバイケースですが、別居による離婚の成立は、大体平均して別居期間が5年以上とされています。
「数か月」「1年」といった単位ではなく、数年単位を要する可能性を考慮し、実行しましょう。
2.調停を申し立てる
夫から離婚を拒否され、「まったく話にならない」ときには、家庭裁判所に「夫婦関係調整調停(離婚)」を申し立てると良いかもしれません。
調停では、調停委員が双方のあいだを取り持ってくれ、夫婦別々に事情を聞いてくれます。したがって、夫が調停の場に参加してくれれば、話し合いをすることが可能です。
ただし、調停の結果は、必ずしも申し立てた側に有利になるとは限りません。夫側の主張の方が理に適っている場合、調停委員の心象は、夫に傾きます。
調停を有利に進めるためには、調停委員を味方につけることが、まず挙げられるでしょう。
更に付け加えれば、初回の調停で決まることはめったにありません。複数回の調停を経て、離婚が成立するケースの方が多いです。
「すぐに離婚できる」とは考えず、長期戦になることを覚悟しておいた方が良いかもしれません。
また、調停にて夫が出席拒否を繰り返した場合、調停は不成立、もしくは棄却される可能性があります。そういった場合はまず、別居をおこない、「実質的な夫婦関係が破綻している」という実績を作った方が良いかもしれません。ただし、実績作りには時間がかかるので、弁護士に依頼することも検討しましょう。
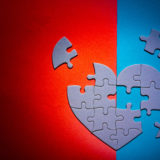 【別居すれば離婚は簡単?】離婚前に別居するメリットとは?
【別居すれば離婚は簡単?】離婚前に別居するメリットとは?
まとめ
今回は、夫が離婚拒否するシチュエーションについてさまざまな観点から考えてきました。離婚したいのに、拒否状態で、離婚ができないといった、八方ふさがり状態の場合には、一度弁護士に相談しても良いかもしれません。
弁護士に状況を伝えることによって、自身では気づいていなかった夫側の離婚事由も発見できるかもしれません。また調停に進んだ場合、代理人として弁護士が参加することも可能です。
弁護士に依頼することによって早期に離婚が成立する可能性もありますので、お困りの際にはぜひ検討してみてください。
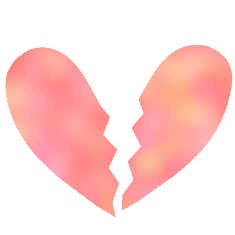 りこんの窓口
りこんの窓口


コメントを残す