子どもがいる夫婦が離婚するとき、必ず考えるべきなのが、養育費です。養育費とは、字面のとおり、子どもを育てるためのお金のことを指します。とても重要なお金なのですが、実情は全体の25パーセント未満のシングルマザーしか、定期的に受け取っていません。
今回は重要な養育費について確認していきましょう。
養育費とは?
そもそも養育費って何でしょう。冒頭では子どもを育てるためのお金とお伝えしましたが、本章ではもう少し具体的に考えていきたいと思います。
養育費とは、非親権者(非監護親)から親権者(監護親)に支払われる子どもを育てるためのお金のことを指します。
日本の制度では、子供のいる夫婦が離婚する場合、どちらが親権を持つのかを必ず決めなければなりません。このことを単独親権と言います。
親権とは子どもに代わって財産管理や契約などの法律行為(※)を行ったり、教育・養育を行ったりする権利です。親権はほとんどの場合、子どもと同居する親が取得します。
親権者が子どもを養育したり、財産を管理したりするのだから、非親権者には親の義務がないと考えてしまう方もいるかもしれません。しかし、離婚をして親権を取得できなかったとしても、法律上その子どもの親に変わりはありません。そのため、非親権者であっても、子どもの扶養義務が生じます。
扶養義務とは、自力で生活ができない親族に仕送りをしたり、現物支給をしたりして経済的なサポートをする義務のことを指します。
当然のことながら、未成年の子どものほとんどは自力で金銭を稼ぐ術を持っていません。そのため、扶養する必要があるのです。
扶養義務は離婚したとしても、免除されることはありません。養育費というかたちで、義務を果たすべきなのです。
養育費の相場は?
養育費は法律上、上限は決められていません。夫婦の話し合いで同意を得られれば、どのような金額でも取り決めることができます。
極端な話、月額100万円だろうが、1,000万円だろうが取り決めを行うことができるのです。
しかし、上記の金額はとてもじゃないですが、現実的とは言えません。例えば、100万円を取り決めたとして、相手方に支払い能力が無ければ、不払いが生じます。そのため、相手方の収入に見合った養育費の取り決めを行う必要があります。
といっても、養育費の目安なんて、ほとんどの方がご存じないと思います。どのように設定するか困ってしまう方もいるでしょう。
そういった場合には、裁判所で公表されている養育費算定表を参考に取り決めを行うと良いでしょう。
養育費算定表では、次のようなものを考慮して作成されています。
- 夫の年収(給与所得/自営業)
- 妻の年収
- 子どもの年齢区分(0~14歳/15~20歳)
- 子どもの人数(1人/2人/3人以上)
養育費算定表は夫の年収が同じであっても、その夫婦の事情が考慮されます。
少しわかりにくいと思いますので、次の例をご確認ください。
①5歳の子どもが1人おり、夫の年間給与所得が800万円、妻の年間給与所得が350万円の養育費相場
表1 養育費・子1人表(子0~14歳)から確認すると、養育費の相場は、6万円から8万円。
②16歳の子どもが一人おり、夫の年間給与所得が800万円、妻の年間給与所得が350万円の養育費相場
表2 養育費・子1人表(子15歳以上)から確認すると、養育費の相場は8万円から10万円。
③8歳と15歳の子どもが2人おり、夫の年間給与所得が800万円、妻の年間給与所得が100万円の養育費相場
表4 養育費・子2人表(第1子15歳以上、第2子0~14歳)から確認すると養育費の相場は12万円から14万円
上記①から③は夫の年収は同じですが、養育費の相場がそれぞれ違います。子どもの年齢区分、人数、妻の年収などによって同じ年収であってももらえる金額に開きがあるわけです。
養育費は、一律で○○円と決まっているわけではないので、請求額が知りたい方は、必ず自分にあった算定表で確認することをおすすめします。
 熟年離婚増加中|熟年離婚で考えておくべき財産分与とは??
熟年離婚増加中|熟年離婚で考えておくべき財産分与とは??
養育費の取り決めを離婚前にするのはなぜなのか
養育費の取り決めは、離婚前にしておくべきであるとよく耳にします。
養育費の請求自体は、子どもが経済的に自立していない状態であれば、離婚後でも取り決めすることができます。
離婚後であっても取り決めができるのであれば、離婚前に時間を割いて決めなくても良いのではないかと考える方もいるかもしれません。
しかし、養育費を離婚前に取り決めておかないと、損をする可能性が高くなるのです。一体どういうことなのか。養育費を離婚前に決めておくべきおもな理由は次の通りです。
- 離婚前に養育費を取り決めておかないと、相手方と密に連絡を取れなくなる可能性がある
- 離婚前に養育費を取り決めないと、請求を行う前までの過去分を請求できない可能性がある
離婚前に養育費を取り決めておかないと、相手方と密に連絡を取れなくなる可能性がある
離婚前に養育費を取り決めておくべき理由として、相手方との連絡がうまく取れなくなる可能性がある点が挙げられます。
離婚前ならば、夫婦が同居しているケースが多いです。同居している場合、夫と連絡が取れないというトラブルに見舞われることは少ないでしょう。
別居のケースであっても、夫婦関係にあるのならば、比較的夫の所在を把握することができます。そのため、養育費の取り決めを行う環境を整えやすいです。
一方で離婚してから取り決めようとすると、なかなか相手方と連絡が取れず、取り決めすることができない可能性が高くなります。
離婚後でも養育費の請求は可能ですし、調停で取り決めすることも可能です。とはいえ、裁判所に調停の申し立てをする場合、相手方の現住所等の情報が必要になります。相手方が黙って引っ越しした場合、所在地を掴むのに時間や面倒な手続きが増えると予想されます。そのため、離婚前に取り決めを行っておいた方が良いのです。
離婚前に養育費を取り決めないと、過去分を請求できない可能性がある
養育費は、法律上その子の親であれば、必ず支払いする義務があります。しかし、実際は、親権者(監護者)から請求を行わないと、支払いが認められないケースが多いです。
つまり、離婚前に取り決めを行えば、養育費の支払い義務は、離婚直後から生じますが、取り決めをしていないと、請求を行った日時からの換算になります。
したがって離婚したときから、養育費の支払い請求を行った日のあいだに発生した養育費は支払ってもらえない可能性が高いのです。
請求した日が、養育費の支払いの起点になるので離婚前に取り決めを行った方が良いのです。
また、養育費を取り決めず、離婚を行った場合には、できるだけ早く相手方にメールや書面で請求を行った方が良いです。
なぜ請求をメールや書面で行うかと言えば、「養育費を請求した」という事実をしっかり残す必要があるからです。証拠の残らない口頭でのやり取りですと、相手方が、「請求されていない」と言って水掛け論になってしまうことがあります。
そのため、できるだけ証拠が残るように請求した方が良いのです。
 【離婚後の養育費】離婚後の養育費の取り決めを変更するにはどうすればいいの?
【離婚後の養育費】離婚後の養育費の取り決めを変更するにはどうすればいいの?
離婚理由が自分自身に原因があっても養育費を請求できるのか
夫婦の離婚理由はさまざまです。相手方に原因がある場合もあれば双方に原因があるとは言えないこともあります。また、ご自身の有責行為が原因で離婚になるケースもあります。
有責行為とは、民法770条で定義されている次のような行為を指します。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上生死不明
- 配偶者が強度の精神病で回復を見込めない場合
- その他婚姻を継続し難い重大な事由
これらの行為を行った方が親権(監護権)を取得した場合、相手方は養育費を支払わなくても良いのでしょうか。
そんなことはありません。親権者が有責配偶者であっても、養育費を支払うかどうかは別問題です。
例えば、ご自身の不貞行為が原因で離婚したとします。相手方が「○○が原因で離婚したのだから、養育費は支払わない」と主張したとしましょう。
有責行為は離婚の原因であって、養育費の支払いは子どもの扶養義務を果たすことです。離婚と扶養義務は全く別問題なので、相手方は養育費の支払いを拒否することができないのです。
そのため、相手方が養育費の支払いを拒否し続けるのであれば、弁護士への相談か調停を申し立てて養育費の取り決めをするかのどちらかです。
離婚前に調停を申立てする場合は、「夫婦関係調整調停(離婚)」で申立てを行い、離婚後のケースでは、「養育費請求調停」の申立てを行う必要があります。
養育費の取り決めを行っていない場合、離婚から養育費の請求を行うまでの期間に発生する養育費は支払ってもらえないケースがあるので、できるだけ早く請求のアクションを起こしてください。
 離婚後に養育費を払わないなんてアリ?正しく対処するための知恵をご紹介
離婚後に養育費を払わないなんてアリ?正しく対処するための知恵をご紹介
まとめ
今回は養育費について詳しく解説しました。養育費は子どもを育てるための大切なお金です。そのため、離婚前に取り決めておくことがベストです。
しかしながら、様々な事情があり、離婚前に取り決めできない方もいるでしょう。そんな時はできるだけ早く、養育費の請求を行うべきです。
独力で難しいときには、弁護士に相談したり、調停等の手段を検討し、アクションを起こすようにしましょう。
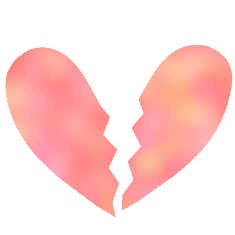 りこんの窓口
りこんの窓口



コメントを残す