夫と離婚したくても、離婚するには相手の合意が大事…。
夫を説得するには、離婚後の生活を見据え、説得しなくちゃ!
離婚後の仕事を決めたり、住居について確認したりとたくさんやることがある。
でも、それだけじゃ足りない?
他にはどんなことをすればいいの?
前編が気になる方は以下をご確認ください。
 【離婚には準備が必要?】専業主婦(夫)が離婚を考える場合にやるべきこと(前編)
【離婚には準備が必要?】専業主婦(夫)が離婚を考える場合にやるべきこと(前編)
離婚する場合には、離婚後を見据えた行動が大事!
専業主婦(夫)の方が離婚を考えた場合、離婚前の準備がかなり重要です。
前編では、離婚前に仕事を決めておくことや、住居についてお話をさせていただきました。
今回は、養育費と育児環境の確保についてお話を進めていきたいと思います。
養育費と育児環境の確保は、離婚後、子どもと生活するうえで、どちらも大変大切なことです。
しかしながら、養育費については未払い問題が多かったり、離婚前に取り決めておかないと子どもにとっても親権者にとっても大きな不利益をこうむったりする可能性があります。
また、離婚後、ひとり親になった場合、今まで相手方が負担していた育児の分もすべてひとりで担わなければいけません。
「全然育児に協力的じゃなかった」「育児には参加していなかった」と思うかもしれませんが、離婚して初めて、案外相手方が育児に参加していたのかと気づくこともあります。
更に付け加えると、子どもが幼い場合、仕事中の保育や子どもの体調が悪くなった場合についても考えておく必要があります。
早速、それぞれ確認していきましょう。
養育費の取り決め
子どもの親権を取って離婚したい場合には、まず養育費の取り決めを必ずすべきです。
子どもがいる夫婦が離婚する場合、日本の法律では、夫婦のいずれか一方が親権を持つこととなります。
親権者となった場合、子どもを教育したり、叱ったり、ご飯を食べさせたり、一緒に生活し、監護養育を行う義務があります。
一緒に暮らさない親を非親権者といい、非親権者には子どもの養育費を支払う義務が生じます。
養育費の支払い義務は、親としての扶養義務を果たすことで、いくら離婚し、非親権者となったからといって、免除されるものではありません。
非親権者が「養育費は必ず支払うものだし、親としては当然のこと」と思って、口約束でも養育費を支払ってくれるひとであればいいのですが、現実的に考えて、そのような人ばかりではありません。
養育費の支払い率は、約2割程度しかありません。
驚くべき低水準ですが、残念ながら現実のお話です。
また、支払われていない方の中には、そもそも養育費の取り決めをしていないというケースも少なくありません。
養育費の取り決めをせず、離婚したために生活が困窮し、子どもの望む進路に行かせてあげられないという家庭もあります。
子どもの将来のためにも、必ず養育費を取り決めておくべきなのです。
 【養育費について考えてみよう】養育費の基本知識
【養育費について考えてみよう】養育費の基本知識
養育費の取り決めは公正証書を活用するべき
養育費の取り決めをするにあたり、次のような方法が考えられます。
- 口約束で取り決める
- LINEやメール等で取り決める
- 離婚協議書を作成し、取り決める
- 公証役場で公正証書を作成し取り決める
養育費を取り決める場合、公正証書で取り決めるべきという言葉を耳にした方もいらっしゃると思います。
どうして公正証書で取り決めるべきなのか、まずはそれぞれの取り決め方のメリットとデメリットを考えていきましょう。
口約束で取り決める
養育費を口約束で取り決めた場合でも、約束が守られるかは置いといて、契約自体は成立します。
例えば、「離婚したら月々○○円の養育費を支払ってね」と口頭で伝えて、相手が「わかった。いいよ。支払うね」といえば、養育費の取り決めをしたことになります。
しかしながら、当然ですが口約束では、契約を交わしたと立証できる証拠が残りません。
そのため、取り決めをしたとしても、約束を破られてしまう可能性が大きいです。
このようなトラブルを防ぐためにも養育費の支払いは、約束が守られないことを見越して、書面で作成した方が良いでしょう。
LINEやメール等で取り決める
LINEやメール等で養育費の約束を取り交わした場合、無効に感じる方もいるかもしれませんが、実は有効です。
強制的に養育費を取り立てる等の効果はありませんが、養育費が滞納された場合、約束を取り決めたという証拠があれば、取り決めた日まで遡って養育費を請求することが可能です。
LINEやメールは履歴を削除しない限り、やり取りした文面は残るので、口約束で養育費の取り決めをした場合よりも、約束を立証しやすいです。
しかし、LINEやメールは、スマホを落として履歴が無くなってしまったり、誤ってメールを削除してしまう等のリスクもありますので注意が必要です。
離婚協議書を作成し、取り決める
離婚協議書で養育費の取り決めを行った場合、その内容が大きく法律に逸脱していない限り、契約書面として有効です。
養育費の未払いがあった場合、即時に強制取り立てをすることができませんが、養育費を取り決めたということを立証できる可能性が非常に高いです。
離婚後、養育費が支払われなくなった場合、養育費請求調停を家庭裁判所に申し立てるときに離婚協議書があると、話し合いを有利に進められる可能性が高くなります。
なお、強制的に取り立てたいと思うのであれば、作成した離婚協議書を公正証書にするか、離婚後であれば養育費請求調停で、調停を成立させ、調停調書を手に入れる必要があります。
離婚協議書は、養育費の取り決めがあったことを立証する重要書面です。
一方で、強制的な取り立てをする効力がほしいのであれば、別途公正証書や調停調書等の公文書が必要なことを覚えておきましょう。
公証役場で公正証書を作成し取り決める
離婚における公正証書は、お住まいの地域を管轄する公証役場に行き、公証人というひとに希望を伝えて作成することができるものです。
離婚協議書との違いは、公文書として養育費が不払いになった場合、給料差し押さえ等の強制執行の手段を盛り込めることです。
強制執行をしたい場合には、公正証書のなかに、「強制執行付き認諾文言」を盛り込む必要があります。
この文言が公正証書にない場合、強制執行を行うことはできません。
したがって、不払い時のリスクヘッジのため、公正証書を作成する場合には、かならず強制執行認諾文言を盛り込んでおくことにしましょう。
なお、公正証書は1契約ごとに、手数料が発生します。
手数料は、契約に盛り込まれている金額によって異なりますので、詳細を確認されたい方は、公証役場のホームページ(リンク貼る)をご確認ください。
養育費は子どもにとっても、親権者にとっても養育を行ううえで大変重要な取り決めとなりますので、多少手数料がかかっても必ず取り決めをしておいてください。
 【絶対作るべき?】離婚するときに離婚協議書を作成する意味とは?
【絶対作るべき?】離婚するときに離婚協議書を作成する意味とは?
育児環境の確保
離婚後の生活を送るうえで、考えるべきことは育児環境の確保です。
前編で、保育園と幼稚園に入る条件の違いを解説しましたので、今回は以下の保育サービスを考えていきたいと思います。
- 認証保育所
- 小規模保育
- 家庭的保育
なお、上記のサービスをご利用の場合、いったん保育所等に保育料を支払い、後で自治体等から、負担分を返却されるケースが多いです。
このような仕組みを償還払いといいます。
償還払いなのか月々のサービス料から引かれるのかは自治体によって対応が異なりますので、詳細につきましてはお住まいの自治体にお問い合わせください。
認証保育所
認証保育所とは、自治体独自に設定した基準に合った認可外保育所のことを指します。
気になるのは、認証保育所を利用した場合、保育料の助成金等があるのかという点でしょう。
結論からいうと、保育料の助成金には、上限設定があり、以下の通りです。
| 子どもの年齢 | 助成金上限設定 |
| 0歳~2歳 | 4.2万円(住民税非課税世帯の場合のみ) |
| 3歳~5歳 | 3.7万円 |
認証保育料が3.7万円を超えている場合には、その分は自己負担となります。
認証保育所は、公立等の認可保育園に比べ、夜遅くまで預かってくれるところが多いので、便利な部分もありますが、一方で認可保育園よりも利用料が高く設定されている場所も多いです。
利用を検討される場合には、事前に保育所や、お住まいの地域の役所に問い合わせを行った方が良いでしょう。
小規模保育
小規模保育とは、認可保育園に比べ、預かり人数が少ない保育所となります。
違いは次の表をご確認ください。
| 保育園種類 | 認可保育園 | 小規模保育A型 | 小規模保育B型 | 小規模保育C型 |
| 園児預かり数 | 20人以上 | 6~19人 | 6~19人 | 6~10人 |
| 職員資格 | 保育士のみ | 保育士のみ | 1/2以上が保育士 | 家庭的保育者(※) |
| 職員数(0~2歳児) | 0歳児(園児に対して3人)
1~2歳児(園児6人に対して1人) |
0歳 園児3人に対して1人
1~2歳 園児6人に対して1人 更に1人追加する |
0歳 園児3人に対して1人
1~2歳 園児6人に対して1人 更に1人追加する |
0~2歳 園児3人に対して1人
家庭的保育補助者を置く場合は 5:2 |
※家庭的保育者とは、市区町村の行う研修を修了し、保育士または保育士と同等以上の知識や経験があると認められたひとを指します。
保育園との大きな違いは、預かる園児が少ないことや、B、Cに関しては保育士資格者の人数の違いです。
小規模保育は、自治体の認証を受けていれば、保育料の一部もしくは、全額助成の対象です。
補助額の負担の上限等は、その施設の価格設定にもよりますので、詳細をご確認されたい方は、お住まいの地域の役所に確認しておきましょう。
ただし、給食費や教材費、延長保育料は無償化の対象外となりますので、ご注意ください。
家庭的保育
家庭的保育というのは、保育士、幼稚園教諭、家庭的保育者等の資格を持ったひとの家に子どもを預入する制度をいいます。
保育場所は、保育士や幼稚園教諭等の自宅等が一般的です。
一度に預けられる子どもの人数は5人以内となりますので、細やかなサービスを受けることができます。
ただし、保育先によっては、子どものお弁当やおやつ等の用意しなければならないところもありますので、注意が必要です。
また、家庭保育に関しても、自治体の認証を受けていれば、保育料の一部、もしくは全額が助成の対象となります。
離婚前に離婚後の子どもの預け入れ先を準備しておくことが大切
ひとり親が子ども保育園に預けたいと考えた場合、他の共働き世帯に比べて入所しやすい傾向にあるというのは事実です。
しかし、公立保育園に入るには、基準点数と調整点数を満たす必要があります。
点数を満たすには家庭状況や就労状況が鑑みられます。
月々の平均の就労が少ない日数かつ、1日の就業時間が短いとその分、点数が減点されがちです。
また、国や地方自治体の施策によって、託児環境が整ってきたとはいえ、大都市部には未だ待機児童が多くいます。
したがって、万が一保育園に入れない場合に備えて、保育園以外の託児先も検討すると良いかもしれません。
まとめ
今回は専業主婦(夫)が離婚を意識した場合に考えておくべきことを前後編で解説してきました。
子どもがいる場合の離婚は、夫婦ふたりだけの時よりも取り決めることが増えます。
そのため、ひとり親の支援策や、託児環境、養育費等、取り決めておくべきことを把握し準備を進めていきましょう。
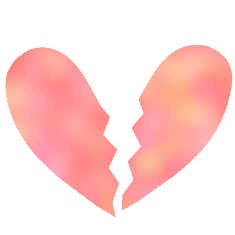 りこんの窓口
りこんの窓口

コメントを残す