離婚する場合、「夫婦で取り決めたことは離婚協議書にしておくべき。公正証書にできればベター」と聞くことがあります。
夫婦が納得のうえ離婚届を出せば、夫婦でなくなるのにどうしてわざわざ夫婦で話し合って離婚協議書を作成しなければならないのでしょうか?
今回は離婚するときに離婚協議書を作成する意味について解説していきましょう。
離婚協議書は「約束」を証明する重要な書類
離婚協議書とは、夫婦が離婚で話し合って決めたことをまとめた書面のことを指します。
離婚する条件は、その夫婦によってそれぞれですが、一般的に取り決めるべきものとして「財産分与」、「親権」、「養育費」等が考えられます。
その他、夫婦の一方が不貞行為やDV等、有責行為をしていたときには、有責配偶者側が支払う慰謝料について取り決めを行います。加えて、離婚に同意する条件として「解決金」を提示していた場合にも慰謝料と同様に支払いについて離婚協議書にその内容を記す必要があります。
離婚協議書を作成する意味とは
離婚協議書は、契約書の一種です。契約は当事者の合意があれば口約束でも成立しますが、後になって相手方から、「そんな約束はしていない」と反故にされてしまう可能性があります。
特に養育費の支払いがあったり、慰謝料が分割払いだったりすると、離婚した後も相手方に継続してお金を支払ってもらう必要があるケースもあります。
相手方が書面にしなくても、滞りなく支払いを続けてくれれば口約束でも全然問題ないのですが、残念ながらそういったケースはあまり多くはありません。
更にいえば、養育費については基本的に子どもが経済的に自立するまでの期間が支払い期間なので、離婚した時期によっては10年以上支払ってもらう必要があります。
離婚後しばらくは相手方も「養育費の支払いをしなければ」という気持ちで支払ってくれるかもしれませんが、離婚から何年も経過すると、相手方の「支払う意思」が薄れて滞納のリスクが高くなります。
未来は不確定要素ばかりなのでリスクヘッジのためにも離婚協議書を作成し、「約束した」という証拠を確保することが大切です。
離婚協議書を公正証書にしておくべきといわれる意味は?
離婚する場合、離婚協議書を公正証書にするべきだという話を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
離婚協議書を公正証書にするには原則として夫婦ふたりで管轄の公証役場に行き手数料を払って、公証人に作成してもらう必要があります。
離婚協議書を公正証書にするのは、多くの場合債務名義となる書面にすることが目的です。
債務名義となる書面とは、養育費等の支払いに滞納があった場合、預金や給料を差し押さえできる強制執行の効力が付与されている書面のことです。
公正証書そのものには強制執行のできる効力が盛り込まれているわけではありません。
強制執行の効力を付与するためには、作成時に公証人へ「強制執行ができる文言を付けてください」と伝えることが重要です。
このように強制執行の効力を持つ公正証書のことを、「強制執行認諾文言付公正証書」と呼びます。
夫婦で作成した離婚協議書は公正証書にするときの素案となる
公正証書にした場合、夫婦が希望すれば強制執行の効力を盛り込むことができます。
一方で、夫婦間だけで作成した離婚協議書には契約を交わしたエビデンスになりますが、その書面でただちに強制執行できるわけではありません。
「強制執行できないのなら離婚協議書を作成する意味なんてない」と思う方もいるでしょう。
結論からいうと、離婚協議書は公正証書にするときの素案となります。
公正証書にするというと、公証役場に赴き、夫婦と公証人3人で話し合うイメージを持つ方もいらっしゃるかもしれません。
しかし実際は、夫婦ふたりで公証役場に赴く前に、公正証書にしたい離婚条件を公証役場にFAX等で事前に共有し、ある程度のすり合わせを行うケースが多いとされています。
このような場合に夫婦間で作成した離婚協議書があるとスムーズに公正証書にしたい内容を公証人に伝えることができるのです。
なお、公正証書は夫婦双方が合意した内容でないと作成することができません。
離婚協議の内容に不満があり、夫婦間で意見の相違がある場合には、公正証書ではなく弁護士に相談するか、または家庭裁判所に離婚調停を申し立てて話し合いを行った方が良いでしょう。
離婚協議書を作成しなくても良いケースもある?
離婚協議書は、「契約が成立した」というエビデンスになるとともに、公正証書を作成したい場合にも重要な役割を果たす書類です。
そのため、本来であればどんな事情で離婚したとしても、必ず作成するべきものになります。
とはいえ、離婚したい方の大半は、「さっさと離婚したい!」と思う方もいるでしょう。
離婚協議書を作成しなくても、トラブルにならないケースはあるのでしょうか。
離婚協議書を作成しなくてもトラブルのリスクが低いケースとして、下記の条件にすべて当てはまっている方が考えられます。
■婚姻期間が短い
婚姻期間が短い場合、夫婦の共有財産の対象となる財産が少ないので、財産分与で争うリスクが低くなります。夫婦の共有財産とは、婚姻関係中に形成された財産のことを指すので、婚姻期間が短いほど少なくなります。
■有責行為がない
有責行為とは、法律で定められている離婚できる理由のことです。相手方の不貞行為やDV、浪費といった行為が原因で夫婦関係の継続が困難な状態になった場合、慰謝料を請求することができます。
有責行為が無い場合、双方が慰謝料を支払う必要が無いので、争いにつながる話し合いをしなくて済みます。
■夫婦双方が離婚の意思を持っている
協議離婚は、夫婦双方が離婚に合意していることが絶対条件です。
そのため夫婦の一方が離婚を拒否している場合には、相手が納得するまで夫婦で話し合うか、調停等で裁判所に仲裁してもらいながら離婚を目指すことになります。
しかし夫婦双方が離婚の意思を持っていれば、「離婚の可否」について争いを避けられることができます。
■子どもがおらず妊娠もしていない
夫婦間に子どもいる場合、必ず親権を決めなければなりません。
夫婦の双方が親権を主張した場合、最悪裁判になるほど熾烈な争いになる可能性があります。
また、離婚前に妊娠していた場合、その子の法律上の父親は婚姻中の夫になります。
仮に実際の父親でなくても、「親子関係不在調停」等を申し立てない限り、婚姻中の夫に養育費の支払い義務が生じます。
子どもがいない、また妊娠をしていないのであれば親権や離婚後の養育費の支払いの取り決めせずにすむので、争いを避けられる可能性が高くなります。
■共有財産に不動産や自動車等の分けにくい財産が含まれない
不動産や自動車等が共有財産に含まれていた場合、金銭とは異なり、きっちり半分に分けることができません。
そのため、誰が不動産や自動車を所有するのか、所有する側の方が多く共有財産を取得した場合、その差額分をどのように補填するか等の話し合いをしなければなりません。
しかし、共有財産が預貯金等の金銭のみの場合には、半分に分けることができるので、その分争いを避けることができます。
以上の条件にすべてあてはまっている夫婦の場合、離婚協議書を作成せずに離婚しても、その後にトラブルになる可能性は低いと予想されます。
言い換えると、この条件いずれかを満たさない場合には、離婚後トラブルに発展する可能性があるということです。
特に子どもがいる夫婦の場合、夫婦関係でなくなっても、子どもの父親と母親として付き合っていかねばなりません。
したがって、親権はもちろん、養育費、面会交流も含めてしっかり話し合いを行い、最低でも離婚協議書として書面を残しておくべきでしょう。
 【離婚するなら必須?】自分で書いた離婚協議書と公正証書の違いについて
【離婚するなら必須?】自分で書いた離婚協議書と公正証書の違いについて
まとめ
今回は、離婚協議書を作成する意味について解説していきました。
法律上の夫婦関係を解消するのは離婚届1枚で事足ります。
しかし、実際は今まで一緒に生活していたわけですから、「それではさようなら」と簡単にいかないケースが多いです。
そのため離婚協議を行い、お互いがすり合わせした結果を離婚協議書にまとめることが大切です。
話し合いの過程で双方の主張に折り合いが付かない場合には、そのまま二人で無理やり話し合おうと思わず、弁護士に相談したり、離婚調停を検討してみてください。
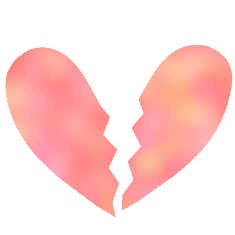 りこんの窓口
りこんの窓口



コメントを残す