依存症とは、お酒やギャンブル、薬物など特定の何かをやめたくても、自分の意思ではなかなかやめられない状態のことを指します。
今回は、離婚トラブルに発展する依存症の状態とは具体的にどのようなことなのか、また離婚する場合に有責行為になるのかなどについて解説していきたいと思います。
- 依存症で離婚トラブルに発展する状態とは?
- 依存症は有責行為とされる場合があるのか
- 依存症を理由に離婚する場合、慰謝料を請求することができるのか
- 配偶者が依存症であることを理由に離婚を考えたときに確認すべきこと
- まとめ
依存症で離婚トラブルに発展する状態とは?
依存症は大きく、「物」に固執してしまうタイプと「プロセス」に固執するタイプと2つがあります。
「物」に固執するタイプは、お酒や食べ物を多量に摂取したり、煙草がやめられなかったり等が考えられます。
対して、「プロセス」に固執するタイプは、ギャンブルをすること、買い物をすることなど、一定の行為がやめられない状態が考えられます。
物とプロセス、どちらにもいえるのは継続していくことで、より強い刺激を求めることが挙げられます。
とはいえ飲酒やギャンブルなどは家族の許容範囲内であれば、問題ありません。
依存者の生活が破綻したり、家族が負担になったりと実生活にトラブルが生じたときに対策が必要になります。
 アルコール依存症で夫が暴力~酒に依存が過ぎる彼と離婚したい~
アルコール依存症で夫が暴力~酒に依存が過ぎる彼と離婚したい~
依存症は有責行為とされる場合があるのか
配偶者の依存症の状態によっては、離婚を考える方が少なくないと思います。
依存症を有責行為として配偶者と離婚することはできるのでしょうか。
民法第770条には裁判上で離婚できる事由が定められており、精神疾患に関して次のように決められています。
具体的にいうと、配偶者が重度の統合失調症やうつ病を患い、この先回復が見込めない場合には裁判で離婚請求ができるという意味です。
回復の見込みのない重度の精神病は夫婦関係が維持できないとみなされ、離婚が認められる場合があります。
依存症は、回復の見込みのない重度の精神病として認められるのでしょうか。
依存症は医療機関で診察を受け、適切な治療を行えば治る見込みのある病気です。
そのため、回復の見込みのない重度の精神病を理由に離婚することはできません。
依存症による行動によっては有責行為になりえる
依存症は、回復の見込めない重度の精神病としては認められませんが、依存症状が原因で引き起こした行動が有責行為として認められるケースがあります。
例えば次のような行動をいいます。
- 飲酒したいという衝動がやめられず家計のお金のほとんどを浪費してしまう
- 過度な飲酒により暴力をふるったり、暴言を吐いたりする
- ギャンブルしたい衝動が抑えられず多額の借金をする
- 飲酒やギャンブルで生活リズムが破綻し仕事を辞めてしまう
継続的にこれらの行為が行われた場合、依存症の方だけではなく家族の生活も立ち行かなくなってしまいます。
そのため、裁判で離婚請求ができる「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に当てはまる可能性があります。
 こころの病を理由に離婚を切り出された!精神病は離婚事由になるのか
こころの病を理由に離婚を切り出された!精神病は離婚事由になるのか
依存症を理由に離婚する場合、慰謝料を請求することができるのか
配偶者が依存症になったことを理由に離婚した場合、必ずしも慰謝料が請求できるわけではありません。
というのも、離婚の慰謝料は、相手の有責行為によって精神的苦痛を受けたことで請求権が生じるからです。
少しむずかしいと思いますので、2つの具体例を交えて解説していきたいと思います。
配偶者の依存症を理由に慰謝料が請求できる可能性が低いケース
夫:俊也さん(仮名)
妻:伊予さん(仮名)
俊也さんと伊予さんはそれぞれ別の会社で正社員として働いている。
俊也さんの業務量は非常に多く常に忙しい。
仕事に関して大きなストレスを感じた俊也さんは毎日酒を飲むようになった。
はじめのうちは500ミリリットルの缶ビール1本程度だったが、半年後には毎日缶ビールを5本飲むようになった。
俊也さんは飲酒をすると伊予さんに暴言を吐くようになった。
伊予さんは俊也さんに離婚するか病院で治療を受けるかどちらか選択してと伝えた。
俊也さんは離婚したくなかったのですぐに病院で診察を行い、治療を開始した。
治療開始直後、伊予さんは懸命にサポートしていたが、何か月経ってもなかなかうまくいかなかったので、結局伊予さんは離婚を切り出した。俊也さんは伊予さんの決意が固いと感じ了承した。
上記の例の場合、俊也さんはご自身がアルコール依存症であることを伊予さんの言葉で自覚しました。
治療前は伊予さんにストレスをぶつけていたものの、自覚して以降は病院で診察をし、治療に専念しました。
また伊予さんも俊也さんが依存症の治療をサポートしたことで、治療前の俊也さんの行動に対しては宥恕(ゆうじょ)したとみなされる可能性が高いです。
宥恕とは寛大に許すことを指すので、慰謝料が請求できないと思われます。
配偶者の依存症を理由に慰謝料が請求できるケース
夫:かいじさん(仮名)
妻:なぎささん(仮名)
かいじさんは正社員として企業に勤めており、なぎささんはスーパーでパートとして働いています。
かいじさんは結婚前からお酒が大好きでした。
なぎささんは、かいじさんがお酒でたびたび失敗していることがあったので、「酒量を控えてほしい」と伝えました。
しかし、かいじさんはなぎささんの訴えに聞く耳を持たず、「病気扱いするのか!」と怒りだし、暴力をふるいました。
なぎささんは暴力をふるわれたことに恐怖を覚え、それ以降かいじさんの飲酒を止めることができませんでした。
かいじさんは「なぎささんを黙らせるには暴力が有効」と考え、飲酒すると日常のうっ憤を晴らすように暴力をふるうようになりました。
なぎささんは日常的に暴力をふるわれることに我慢できず、離婚を切り出しました。
上記のかいじさんの行為は離婚訴訟を提起できる裁判上の離婚事由にあたる可能性が高いです。
アルコール依存症そのものを理由に慰謝料を請求することはできませんが、過度のアルコール摂取によって日常的に暴力をふるう行為は身体的DVです。
身体的DVは他人の権利を侵害する行為ですので、なぎささんは精神的苦痛を受けたことを理由に慰謝料を請求することができます。
また、身体的DVの場合、精神だけでなく身体的な苦痛も受けているため、治療費なども請求することが可能です。
 【離婚の法律用語】離婚に関するモラハラ知識について知ろう
【離婚の法律用語】離婚に関するモラハラ知識について知ろう
配偶者が依存症であることを理由に離婚を考えたときに確認すべきこと
配偶者の依存症を理由に離婚を考えた場合、次のような点に着目して、実際に離婚するかどうかを決めた方が良いでしょう。
配偶者が依存症であることを自覚し治療する意思があるのか
本当に離婚するかどうかを考えるポイントとして、依存症であることの自覚、また医療機関で診察を受け、治療する意思を見せているかどうかです。
ご自身が配偶者に「病院に行ってほしい」ということを伝え、応じてくれるのであれば配偶者側にも夫婦関係を維持するための努力がうかがえます。
反対に聞く耳を持たなかったり、逆上して暴言などを吐いたりする態度の場合には、この先も夫婦関係を維持するような行動をとる可能性が低いと思われるので離婚を決断しても良いかもしれません。
依存症のサポートを長期間行えるのか
依存症のサポートは本人の努力も大切ですが、家族の負担も大きなものです。
配偶者が依存症の治療に積極的である姿をみて、完治するまで献身的なサポートをずっと行うことができれば一番良いのですが、生活が安定するには長い時間がかかると想定されます。
そのため、はじめのうちはサポートしたいと考えていても、生活が安定するまでの期間が長いと、精神的に追い詰められることもあるでしょう。
我慢しすぎるとかえってご自身が精神疾患になってしまうこともありますので、そうなる前に離婚することも選択肢のうちです。
まとめ
今回は依存症について詳しく解説していきました。
依存症は「心が弱いひと」や「我慢がきかないひと」がなると思われがちですが、実際にはストレスを限界まで我慢するひとの方が発症しやすいといわれています。
配偶者が依存症を発症したこと自体は仕方ないかもしれませんが、それによって夫婦関係が続けられないと感じたときには離婚を検討してみても良いかもしれません。
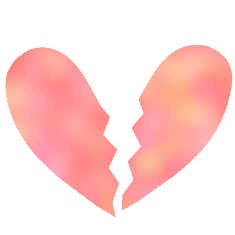 りこんの窓口
りこんの窓口



コメントを残す