夫婦が離婚するときには条件を取り決めてから離婚届を出すという考えの方が多いと思います。
しかし、実際には離婚後に条件を取り決めることもあります。
今回は離婚後でも取り決められることや請求方法などについて解説していきたいと思います。
夫婦の合意と子どもの親権者さえ決めれば離婚可能
夫婦関係が悪くなり離婚したい場合、夫と妻がどちらも離婚することに納得すれば成立させることができます。
子どもがいる夫婦の場合には、夫婦双方の合意の他に親権者の決定が必要ですが、この2つの条件をクリアすれば、紙1枚で離婚が成立します。
海外の離婚手続きには、裁判所にいって裁判を受けたり、離婚に熟慮期間が設けられていたりするところもあるので、当事者同士が納得すれば離婚が成立できる日本の離婚制度はとても簡単な手続きといって良いでしょう。
とはいえ離婚というと取り決めることがいっぱいあるというイメージを持つ方は少なくないと思いますが、実は離婚の取り決めのうち親権以外のものについては離婚後でも取り決めることができます。
それぞれ確認していきましょう。
離婚後の取り決め①財産分与
離婚後に取り決めができるものとして財産分与が挙げられます。
財産分与の対象となる夫婦の共有財産は、婚姻届を出してから離婚が成立する日(または別居日)までの期間に築いた財産が対象です。
なお、個人的な身分によって取得した財産、例えば相続や贈与によって取得した財産は、共有財産には含まれません。
財産分与は離婚後2年を経過してしまうと時効が完成します。
そのため離婚してから2年以内に財産分与を請求する必要があります。
離婚後の財産分与する方法については、まず共有財産の洗い出しから始まります。
その後、元配偶者と話し合いを行い、具体的に取得する財産や取得する財産の割合を決めます。
相手が財産分与などの取り決めに積極的に参加してくれるようであれば問題ないのですが、中には財産分与をすることが嫌になって話し合い自体を拒否する人もいます。
このような場合、何もせずにいると時効が完成してしまう恐れがあるので、財産分与請求調停を家庭裁判所へ申立てることを検討してみてください。
また当事者同士で折り合いがつかないときにも調停がお勧めです。
調停では、当事者同士が顔を合わせて主張することはあまりなく、多くの場合調停委員という仲裁役が別々に事情を聞きます。
顔を突き合わせて当事者が話すよりも、感情的にならず冷静に話し合いができる可能性が高まります。
 【相談事例】共有財産に不動産が含まれる場合の財産分与はどうすればよい?
【相談事例】共有財産に不動産が含まれる場合の財産分与はどうすればよい?
離婚後の取り決め②養育費
離婚後に取り決められるものとして、養育費が挙げられます。
養育費とは、子どもと同居していない親に支払い義務のあるお金です。
養育費は民法第877条で定められている扶養義務から支払い義務が生じます。
通常の借金の返済義務のように、具体的な金額が決められていないため、養育費は相手方に請求した時点から請求権が生じます。
つまり、離婚後、相手方に養育費を請求するアクションを起こさず、後になって相手に「過去の分の養育費を支払ってよ」といってももともと請求権がないため、相手に支払ってもらうことができないのです。
養育費を取り決めずに離婚した場合には、離婚後すぐに「養育費の取り決めを行いましょう」と相手に通知してください。
相手が養育費の取り決めに非協力的な様子であれば、こちらもすぐに養育費請求調停を家庭裁判所に申し立てましょう。
調停で希望する養育費の金額を満額もらえるかはわかりませんが、少なくとも養育費の取り決めを行うことができます。
調停で取り決めを行えれば、取り決め後に滞納があった場合、強制執行などの手段も行うことができます。
なお養育費請求調停が不成立に終わったときには、そのまま審判に移行します。
裁判官は両親それぞれの主張、また収入や子どもの人数、年齢などで算出した養育費算定表などの資料をもとに養育費の金額を決めてくれます。
 離婚後のお金の心配はどうする?養育費の算定や支払いについて知ろう
離婚後のお金の心配はどうする?養育費の算定や支払いについて知ろう
離婚後の取り決め③面会交流
離婚後の取り決めできるものとして面会交流が考えられます。
面会交流とは、離婚などで別居している親子が定期的に会って遊んだり、LINEなどのSNSでやり取りしたり、テレビ電話で会話したりして交流を図ることをいいます。
別居している親との交流を通し、「自分が愛されていること」を知るのは、子どもの養育にとって非常に大切です。
面会交流は、離婚前、離婚後の取り決めに関わらず、子どもの負担とならないように最大限考慮して決める必要があります。
そのため両親がどのような形態で面会交流を行うのかをしっかり話し合うことが大切です。
面会交流を積極的に進めたいと思うのは、おそらく子どもと別居している方が多いのではないでしょうか。
離婚した理由や同居親との関係性によっては、面会交流を求めても一方的に拒否されてしまうということもあるでしょう。
もしも子どもの意思で「別居親と会いたくない、交流したくない」と示されたのであれば、面会交流は子どもの意思が何よりも優先されるので、なかなか難しいかもしれません。
しかし、同居親が子どもの意思関係なく断っていたり、同居親が別居親を貶めるような発言を日常的にして子どもの意思を捻じ曲げているケースもあります。
このように面会交流がうまくいかない場合には、家庭裁判所に面会交流調停を申立てることをお勧めします。
面会交流調停では、調停委員を仲裁役として当事者同士で話し合うほかに、家庭裁判所調査官が親と子どもにそれぞれ事情を聞き、次のようなことを調査します。
- 同居親の監護状況
- 子どもの意向
- 子どもへの心情調査
※調査内容は一例であり、すべての面会交流調停に当てはまるわけではありません。
これらの調査と、両親のそれぞれの希望、主張を整理しつつ面会交流調停は行われます。
調停が両親の意向に折り合いがつかず不成立に終わったときには、そのまま調停は審判に移行します。
面会交流の審判では、担当の裁判官がこれまでの調停の経緯や家庭裁判所調査官の調査結果の内容をもとに審理し、面会交流の頻度を決めてもらうことができます。
なお審判結果に不満がある場合には、審判を受けてから2週間経過する前に、管轄の高等裁判所に不服申し立てを行う必要があります。
審判を受けてから2週間が経過した後に「やっぱり不満だ」と思った場合には再度面会交流調停を申立てなければならないのでご注意ください。
 【面会交流って何?】離婚後、元配偶者と面会交流を取り決めるべき理由とは
【面会交流って何?】離婚後、元配偶者と面会交流を取り決めるべき理由とは
離婚条件の取り決めは離婚前にした方が良い?
離婚条件の取り決めは、できれば離婚前にしておいた方が良いです。
というのも、離婚後に条件を取り決める場合、相手方が協力的でなければなりません。
また折り合いがつかず調停や審判などに進んだ場合、準備をしなければならなかったり、調停期日は平日なので仕事の調整をしなければならなかったりします。
更に言えば、離婚前の離婚調停ならば1つの申し立てで財産分与・養育費・面会交流などを包括的に話し合うことができますが、離婚後は複数申立をしなければならないこともあります。
まとめ
今回は離婚後できる離婚条件の取り決めについて解説していきました。
離婚後の取り決めのうち、財産分与や養育費などのお金の請求に関してはなるべく早く交渉できるように行動した方が良いでしょう。
とはいえ具体的にどのような行動をすればいいのかわからない方もいるかもしれません。
そんな時は、一度弁護士に相談することも検討してみてください。
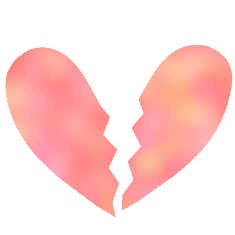 りこんの窓口
りこんの窓口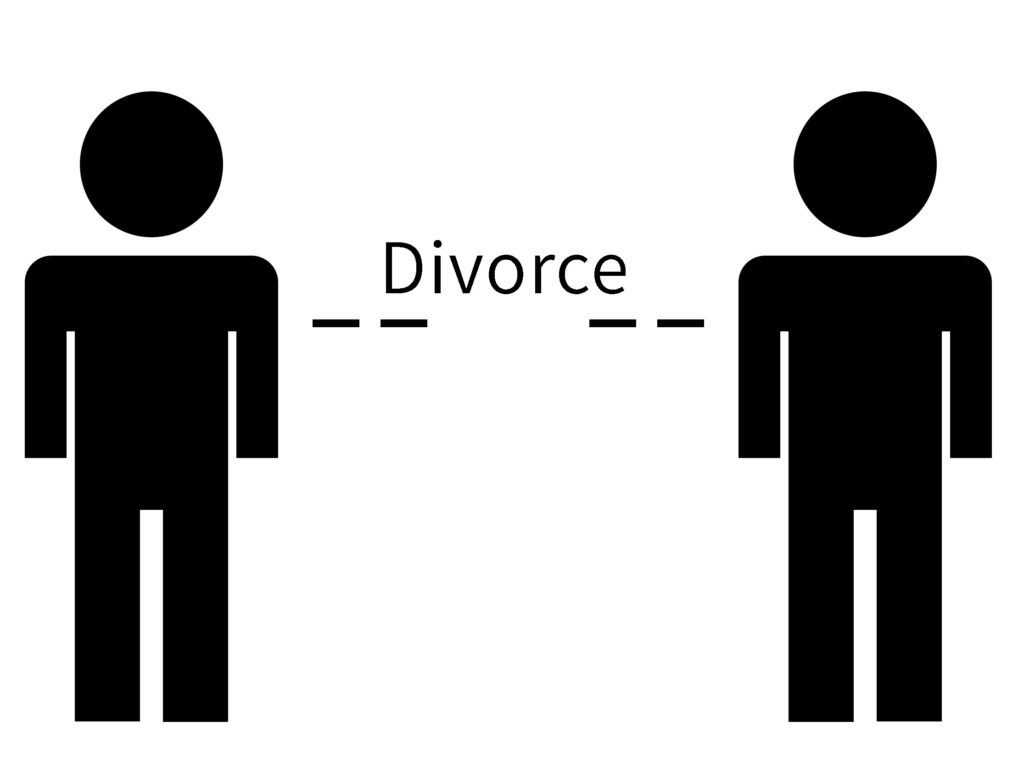



コメントを残す