この記事の情報提供者
離婚調停の流れがわかれば、今後の見通しを立てやすくなります。具体的な手続きや持ち物がわかれば、あなたにとって最適な選択肢がわかるでしょう。
離婚調停って、いったいどんな流れで進むんだろう……この疑問に詳しい桔梗さんに教えていただき、以下についてまとめました。
- 離婚調停とは
- 離婚調停を申し立てる際の流れ
- 離婚調停申立~第1回調停までの流れ
- 離婚調停当日の流れ・持参するもの
- 離婚調停が終了するとき
- 離婚調停が不成立となった場合の対応方法
離婚調停の流れが気になる人は、要チェックです。
離婚調停とは

よく耳にするものの、離婚調停の意味や内容について、しっかりと把握できていない人もいます。離婚調停の基礎知識をご紹介するので、この機会におさえておきましょう。
調停委員を介して離婚の話し合いを進めること
離婚調停とは、調停委員を介して離婚に関する話し合いを進める方法のこと。夫婦のどちらかが事情によって離婚条件に合意できず、離婚の話し合いがまとまらないときなどにおこなわれます。
離婚調停の正式名称は、「夫婦関係等調整調停」。離婚調停は家庭裁判所でおこなわれ、調停委員を介して離婚の話し合いを進めます。
夫婦が直接話し合う協議離婚と異なり、離婚調停では相手と話し合うことはありません。中立的な立場である調停委員を間に挟むため、円滑に話し合いを進められることがあります。
離婚調停で取り上げられる内容
離婚調停で扱える内容は基本的に、離婚に関する話し合いのすべてです。離婚するには、財産分与や年金分割、慰謝料の話し合いが必要となります。また、子どもが居れば親権や養育費、面会交流も取り決めなければなりません。
これらの協議離婚ではなかなか解決できない問題のすべてを、離婚調停で話し合えます。そのため話がもつれた際に、離婚調停を利用する夫婦は少なくありません。
ただし離婚調停はあくまで話し合い。そのため、調停委員が離婚内容を決めるわけではなく、お互いが納得できる条件を模索するだけです。離婚調停で話がまとまらない場合には離婚内容が定まらないので、離婚訴訟を起こすなど別の策を検討しなければなりません。
 【調停離婚】離婚を調停で成立させるメリットとトラブルについて確認しよう
【調停離婚】離婚を調停で成立させるメリットとトラブルについて確認しよう
離婚調停を申し立てる際の流れ

離婚調停における申立ての流れは以下の2つ。わかりやすく解説しますね。
- 必要なものをそろえる
- 申立てをする
離婚調停に必要なもの
離婚調停の申し立てに必要な書類は、以下の7点です。
- 夫婦関係調整調停申立書
- 申立人の印鑑
- 申立人の戸籍謄本
- 相手方の戸籍謄本
- 年金分割のための情報通知書(年金分割を求めていない場合は不要)
- 照会回答書
- 事情説明書等
状況によって必要書類が変わることがありますので、詳細は申し立てをする家庭裁判所へ確認することをおすすめします。
離婚調停に係る費用
離婚調停の申立て費用は約2,000円です。以下の費用がかかりますので、チェックしておいてくださいね。
- 収入印紙:1,200円
- 郵便切手:約800円(相手方への連絡費用など)
離婚調停の申立て方法
離婚調停は、原則として相手方の住所地である家庭裁判所で申し立てをすることになっています。そのため、該当の家庭裁判所がどこなのかを調べておくと良いでしょう。

離婚調停申立~第1回調停までの流れ

離婚調停の申立てをしたあと、第1回目の調停までは以下の流れになります。
- 家庭裁判所と日程調整をする
- 調停期日呼出状を受け取る
詳しく見てみましょう。
家庭裁判所と日程調整をする
離婚調停を申し立てると、家庭裁判所から調停日の調整に関する連絡が届きます。空いている時間を確認のうえ、家庭裁判所に希望日時を伝え、第1回調停日を決めましょう。
調停期日呼出状を受け取る
調停日が決定すると、申し立てをした家庭裁判所から夫婦それぞれに調停期日呼出状が届きます。調停期日呼出状が届くのは、申立ててから約2週間後が目安です。
第1回目の調停日は通知を受け取った日の約2週間後になることが多いといわれています。そのため、離婚調停申立後から第1回調停までの期間は、およそ1ヶ月ほどとなるでしょう。
ただしこれはあくまで目安。地域によっては、もっと長くかかる場合もあります。たとえば東京や横浜などの大都市の場合、離婚関係の案件数が多いため、1ヶ月半から2ヶ月ほどかかるケースもあるので要注意。
離婚調停当日の流れ・持参するもの

「当日の流れを知っておくと、不安が少なくなる」でしょう。そこで、離婚調停当日の流れや持ちものについて、お伝えしますね。
離婚調停当日の流れ
離婚調停当日は、以下のような流れで進行します。
- 待合室で待機
- 調停室で諸注意の確認、経緯の説明をする
- 待合室で待機(この間、相手が調停委員と話す)
- 調停室で調停委員と話し合う
- 待合室で待機
- 調停終了
離婚調停当日、家庭裁判所に到着後すると、呼び出されるまで待合室で待機することに。離婚調停では、夫婦が顔をあわせなくてすむよう配慮されており、ある程度の要望も伝えられます。その後、離婚調停の申立人が呼び出され、調停室で調停委員2人と挨拶します(調停委員は基本的に男女1人ずつ)
そこで、調停の進め方や手続きについて説明があり、離婚調停を申し立てるに至った経緯などを30分程度話す流れです。話を終えたら退室し、再び待合室へと戻ります。次に相手方が呼び出され、同様の流れで調停委員と30分ほど話をすることに。
続いて、申立人が再び調停室へと呼ばれ、相手方が主張している内容を調停委員から伝えられます。申立て人と同様、相手の主張に対してどうするか質問され、申立人が回答します。この時間も約30分。
最後に再び相手方が調停室に呼び出され、約30分間調停委員と話すことになります。このように相手と顔をあわせなくて済むような流れで各々が2回ずつ調停委員と話をして、離婚調停は終了に。必要に応じて、次回の案内や持ち物などを伝えられます。

離婚調停に持参するもの
離婚調停当日、持参すべきものは基本的に以下の5つです。
- 期日通知書
- 印鑑
- 身分証明証(免許証や保険証、パスポート等)
- メモ帳(または手帳)
- 筆記用具
場合によって、上記以外のものが必要になるケースもあるので、詳しくは家庭裁判所に確認することをおすすめします。
上記のなかで、とくに大切な書類が期日通知書です。事件番号が記されているので、スムーズに手続きをすすめるために必要となります。家庭裁判所で複数の調停がおこなわれていることは少なくないので、注意しましょう。

 話し合いで解決?~はじめての離婚調停~
話し合いで解決?~はじめての離婚調停~
離婚調停が終了するとき

離婚調停の終了パターンは以下の3つです。
- 調停が成立したとき
- 調停が不成立となったとき
- 調停が取り下げられたとき
調停での話し合いで、夫婦の両方が離婚条件に合意し、調停委員から見ても離婚した方が良いと認めた状態となった時、調停離婚は終了します。反対に、離婚調停においても、話し合いが進まない場合などには、調停不成立となります。
そのほか、調停の申立人が家庭裁判所に取下書を出した場合にも離婚調停は終わることに。取下書の提出をする際、パートナーの同意は不要です。
離婚調停が不成立となった場合の対応方法

離婚調停でも話がまとまらなかった場合、とれる方法は2つです。以下を参考に、どちらが最善の方法か見極めてください。
裁判離婚に進む
離婚調停が不成立となったものの、やはり離婚について白黒つけたいという場合、裁判離婚に進めます。裁判離婚で下される判決には強制力が伴うので、ハッキリとした結果が得られることに。
その反面、手続きにかかる時間や労力が増し、弁護士に依頼するなどの負担も生じます。精神的な負担も増え、苦痛を感じる人も少なくありません。
夫婦で再度話し合う
上記のとおり、裁判離婚は双方にとって負担が大きいので、再度夫婦で話し合うこともひとつの手。裁判離婚にもつれこみ、泥沼になってしまうことを考えることで、双方が歩み寄れることもあるでしょう。離婚内容について妥協して協議離婚で終わらせるか、しっかりと裁判離婚に取り掛かるのか、慎重に決めることが大切です。
まとめ
離婚調停の流れをおさえておけば、今後の見通しを立てやすくなります。どの程度の時間がかかって、どんな風に手続きが進むのかがわかることで、余計な心配も減らせるでしょう。
調停委員を介することで、冷静に話し合いを進め、うまく離婚できるかもしれません。その一方で、先述のとおり離婚調停には強制力がありません。「離婚調停をしたけど、結局なにも話が進まなかった…」ということもあるのです。
この点を理解し、あなたの今後につながる選択をしてくださいね。
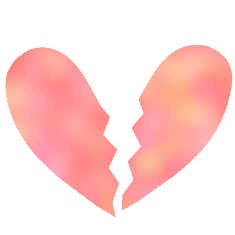 りこんの窓口
りこんの窓口

