熟年離婚とは一般的に夫婦の年齢関係なく婚姻期間が20年以上の夫婦が離婚することを指します。
とはいえ、日本の初婚年齢は20年前から男女ともに30歳前後になりますので、大体50歳以上の方の離婚を熟年離婚といって良いかもしれません。
今回は婚姻期間が長い夫婦の離婚の難しさを詳しく解説していきたいと思います。
熟年離婚の大変さ①財産分与が複雑になる
熟年離婚を行う場合の大変さとして分け合う財産が多くなるので、財産分与が複雑になることがあります。
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦ふたりで築いた共有財産を分けることです。
共有財産の対象となる財産は、婚姻前に築いた財産、相続や贈与など夫や妻が個人的に取得した特有財産を除いた財産のことをいいます。
なお特有財産であっても、同じ口座で管理しているなど区別がつかないものに関しては、共有財産としてみなされます。
財産分与は、特別な事情がない限り、夫婦それぞれに共有財産の半分を受け取る権利があります。
共有財産の額は一般的に婚姻期間が長ければ長いほど大きくなります。
また次のような共有財産は婚姻期間の長さによって取得できる相場が異なります。
- 退職金
- 婚姻前から加入していた生命保険の解約返戻金
- 年金分割
退職金
退職金は、後払いの給料とみなされます。
婚姻期間中の給料は、当然夫婦の共有財産となりますので、退職金は財産分与の対象になります。
共有財産の対象となる退職金は、その会社で働いていた期間と婚姻期間が重なった部分です。
勤続年数が少なかったり、婚姻期間が短かったりした場合、退職金が財産分与の対象になることはほとんどないです。
しかし熟年離婚の場合、退職金が財産分与の対象となる可能性が非常に高いです。
夫婦間が退職金について冷静に話し合える状態であれば良いですが、すでに関係が壊れているようなケースの方が多いと思いますので、話し合いが難航することが予想されます。
婚姻前から加入していた生命保険の解約返戻金
生命保険は社会人になったタイミングや結婚したタイミングで加入される方が多いのではないでしょうか。
まず、結婚してから加入した生命保険は、家計から掛け金を捻出しているのでその解約返戻金が財産分与の対象となります。
また、結婚前に加入した生命保険に関しても、婚姻期間中に加入していた期間については財産分与の対象となります。
離婚する場合、一度生命保険を解約して、その返戻金をそれぞれの夫婦に分配することになると思いますが、生命保険は年齢があがるごとに掛け金があがったり、条件が悪くなったりします。
そのため、生命保険を解約したくない場合は返戻金に相当するお金を支払わなければならないケースもあります。
複雑な場合には、弁護士に連絡した方が良いと思います。
年金分割
年金分割とは、婚姻期間中に夫婦が加入していた厚生年金部分について、それぞれ報酬額に応じて分け合うことをいいます。
年金分割は、婚姻期間が長いほど将来受け取れる年金が増える可能性があります。
夫婦間での話し合いが必要になるのはもちろんのこと、分割の合意がとれたとしても、年金事務所などで手続きが必要なので手間が増えます。
 【共有財産はお金だけじゃない】離婚時にもめる可能性のある財産分与
【共有財産はお金だけじゃない】離婚時にもめる可能性のある財産分与
熟年離婚の大変さ②相手が認知症になった場合離婚できない可能性もある
熟年離婚の大変さとして、相手が認知症になった場合、離婚するまで長引いたり、最悪の場合離婚できなかったりします。
軽度の認知症であれば、相手方もある程度判断がつくので双方の合意があれば離婚を成立することができます。
しかし、認知症がかなり進行して日常生活に支障がある場合、最終的に裁判で離婚を認めてもらう必要があります。
重度の認知症は、法律で定められている離婚事由のひとつ、「配偶者が強度の精神疾患で回復が見込めない場合」に該当します。
ただし、離婚裁判で回復を見込めない強度の精神疾患を理由に離婚が認められるには、「離婚後精神疾患のある配偶者が生活できること」が条件です。
つまり、離婚後相手方が困窮せずに生活できる環境を作ったり、継続的に金銭面のサポートを行ったりしなければならないこともあります。
「離婚後までなんでサポートしなくちゃいけないの?」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、日本国憲法ではすべての国民が「健康で文化的な最低限度の生活」を送る権利が保障されています。
そのため、裁判所も離婚したら生活が破綻することが明らかな場合には、離婚を認めません。
したがって、相手の判断能力がはっきりしているうちに離婚を切り出した方が良いです。
 こころの病を理由に離婚を切り出された!精神病は離婚事由になるのか
こころの病を理由に離婚を切り出された!精神病は離婚事由になるのか
熟年離婚の大変さ③生活が困窮するおそれがある
熟年離婚の大変さとして、離婚後の生活が困窮するリスクがあることです。
「とにかく離婚したい」という気持ちが強く、離婚成立を目的とした場合、財産分与などの取り決めがおざなりになってしまうと、後になって金銭的に苦しくなってしまいます。
ある程度年齢が若ければ自分で働いて収入を得ることができますが、高齢の場合、働こうと思っても雇用の間口が狭く、なかなか思ったような仕事に就けないのが現状です。
そのため、熟年離婚をする場合には金銭面についてしっかり取り決めをする必要があります。
熟年離婚の大変さ④子どもへの影響を考える必要がある
熟年離婚するタイミングとして、子どもが高校や大学を卒業して社会人になり、育児が終了したときが考えられると思います。
熟年離婚を選択した場合、すでに子どもの育児が終了しているケースが多いかと思いますので、子どもが受ける影響は最小限に抑えられると思う方もいらっしゃるかもしれません。
確かに子どもが親から自立している場合には、親の離婚が与える精神的負担は低くなるといって良いでしょう。
しかし熟年離婚は子どもの介護負担が大きくなる可能性があります。
夫婦は離婚すれば他人になるので、元配偶者に介護が必要になったとき、法律上なんの義務も負いません。
一方で子どもの場合、両親が離婚したとしても法律上の父親と母親が変わるわけではありません。
そのため父親や母親に介護が必要になった場合、その親を扶養する義務が生じます。
法律上の子どもが親を扶養する義務は努力義務なので、親から子どもに生じる扶養義務よりも弱く、「経済的な余力がある範囲内で扶養すればいい」とされています。
とはいえ、親の介護をめぐって兄弟仲が悪くなったり、「親だから」という思いから金銭的、精神的に無理してしまったりすることもあります。
介護は、状況によって金銭的、精神的に大きな負担になりえます。
したがって熟年離婚をする際には、介護についてご自身の子どもにも伝えることが大切です。
弁護士に相談したい方はこちら熟年離婚は将来を見据えて準備すべき
熟年離婚をする場合、さまざまな取り決めや準備を行う必要があります。
準備や周りへの根回しが不十分だと、金銭的に困窮したり、子どもとの関係が険悪になったりする可能性があります。
離婚することで生じるリスクを低くするには、弁護士への依頼を検討した方が良いでしょう。
熟年離婚の大きなハードルである財産分与についての相談はもちろんのこと、相手が離婚を拒否した場合の対応、離婚前の準備に対するアドバイスなどさまざまなサポートをしてくれます。
弁護士への相談や依頼というと、「費用が高いのではないか」と思い悩む方もいらっしゃるでしょう。
しかし、離婚の取り決めが不十分だったり、折り合いがつかず争いが長引いたりした場合、身体的、精神的に大きな負担となり得ます。
その点、弁護士に依頼すれば代理人となってさまざまな手続きを代わりにしてもらうことができます。
また、費用面についても協議離婚の場合の弁護士費用の相場は大体40万~60万円といわれています。
一見高いようにも思えますが、自力で離婚の手続きを進める負担やそこにかかる時間をお金で買ったと考えると見方が変わってくる方もいらっしゃるのではないかと思います。
まとめ
今回は熟年離婚の大変さについて紹介していきました。
熟年離婚を決意した方は、20年以上の夫婦関係を切ると決断したわけですから、並大抵の覚悟ではないでしょう。
また、夫婦である期間が長い分だけ、相手に対する不満や怒りなどのマイナスの感情は大きいと思います。
相手に対する悪感情が大きいと当事者間での話し合いは困難をきわめますので、その場合には離婚調停、弁護士への依頼を検討しましょう。
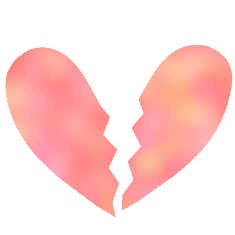 りこんの窓口
りこんの窓口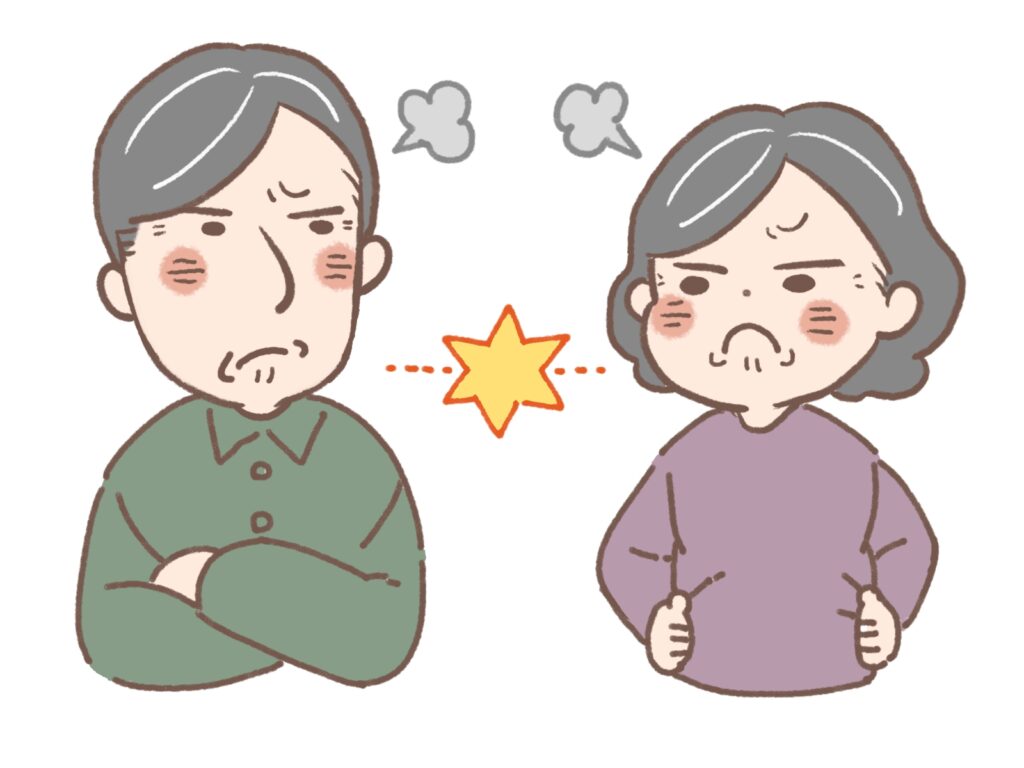



コメントを残す