離婚が成立すれば、元夫との関係がすべて断ち切れるわけではありません。
よく挙げられる離婚後のトラブルとして、養育費の不払いがあります。
養育費は子どもの年齢によって、10年、15年以上支払いが続くお金です。
今回は、養育費の支払いが滞ってしまった場合に行うべきことをケース別で紹介していきたいと思います。
養育費の不払いは養育費の取り決め方によって大きく異なる!
元夫からの養育費の支払いが滞り、不払いになったとき離婚条件をどのように取り決めたかによって、次の行動が異なります。
それぞれどのような行動をすればいいのか確認していきましょう。
離婚協議書で取り決めした場合
離婚する夫婦の8割は協議離婚をするので、夫婦間で離婚協議書を作成するケースは少なくないと思われます。
離婚協議書とは、ざっくりいうと離婚する条件をまとめた契約書のことです。
内容は、離婚する理由などさまざまな要因で異なりますが、子どもがいる夫婦の場合、月々の養育費や支払期間、毎月養育費を入金する期日、入金する銀行口座などを記載します。
離婚協議書は夫婦が合意すれば作成できるので、費用面や手間を考えて公証役場や裁判所が介さずに作成する方が多いと思います。
養育費を取り決めて不払いになった場合、まずは元夫に対して養育費の支払いについて確認をとってみると良いでしょう。
連絡がついた場合には、養育費が滞った理由、引っ越ししていそうだったり、転職していたりといったことがありそうなら、新しい住所や会社名を聞き取りすることも良いと思います。
話し合いで支払いを拒否するようであれば、養育費請求調停を申し立ててください。
というのも夫婦間で作成した文書は、私署証書といって法的に給料や口座の差し押さえといった強制執行ができる効力がないからです。
養育費請求調停を家庭裁判所に申し立てて成立すれば、債務名義といって強制執行できる効力がある調停調書を手に入れることができます。
まずは強制執行ができる債務名義を取得することを考えましょう。
離婚協議書を公正証書とした場合
離婚協議書を公正証書とした場合、まずはその中に「強制執行認諾文言」があるかどうか確認してみましょう。
強制執行認諾文言とは、次のような文言の事を指します。
第〇条
〇は第〇条(養育費について記載された条項)の債務の履行を遅滞したときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。
上記がお手元にある公正証書に無い場合、公正証書であっても強制執行をすることができません。
そのため強制執行をしたい場合には、家庭裁判所で養育費請求調停を申し立てる必要があります。
公正証書に強制執行認諾文言がある場合には、公正証書を作成した公証役場に行き、以下の手続きを行う必要があります。
- 送達…公正証書の正本または謄本の送達の申し立てを行い、公証人が債務者に対して送達をし、送達証明書を受け取る。
- 執行文付与…公証人に公正証書の正本に執行文を付与してもらう
1、2の手続きを済ませたら、次は元夫が住んでいる地域を管轄している地方裁判所に強制執行の申し立てを行います。
ご自身が住んでいる地域を管轄している地方裁判所ではないので、ご注意ください。
離婚調停や裁判で取り決めした場合
離婚調停や審判、裁判などで取り決めをした場合、履行勧告と強制執行の2つの取り立て方法があります。
履行勧告とは、裁判所に元夫からの養育費の支払いが滞っていることを伝えることで、支払うよう促す制度の事をいいます。
履行勧告は離婚調停や審判、裁判などを行った家庭裁判所に申し立てることで、家庭裁判所が調査をしたうえで勧告をします。
なお、履行勧告はあくまで支払いを促す制度であって、支払うかどうかは相手次第です。
養育費の支払いを強制するものではありませんので注意が必要です。
強制執行を行う場合は、調停や裁判などをした家庭裁判所に送達証明書の交付を申請する必要があります。
なお、取得した債務名義が和解調書や判決書の場合、別途家庭裁判所にて執行文の付与の手続きをしてください。
家庭裁判所での手続きを終えたら、強制執行の申し立てを元夫が住んでいる地域を管轄している地方裁判所に行います。
強制執行の手続きは家庭裁判所ではなく地方裁判所になるので間違えないようにしてください。
何も取り決めをしなかった場合
離婚時に何も取り決めをしなかった場合には、すぐに養育費請求調停を家庭裁判所に申し立ててください。
養育費は子どもの親である以上必ず支払うべきお金ですが、法律で具体的に支払う金額が決められているわけではありません。
そのため離婚後何も取り決めていない期間の養育費は請求することができないのです。
養育費を取り決めしておらず、今後養育費を請求したいと考えている方は、まず養育費請求調停をすることを考えましょう。
 【養育費について考えてみよう】養育費の基本知識
【養育費について考えてみよう】養育費の基本知識
強制執行にかかる費用は?
公正証書や調停調書などがあれば、簡単に強制執行ができると考えている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、強制執行は簡単にできるものではなく、さまざまな手続きが必要ですし、費用も発生します。
強制執行を行った場合、どのような費用が発生するのか確認していきましょう。
申し立て費用
強制執行の申立て費用は、取り立てたい債務者1人につき、4000円の費用がかかります。
養育費の場合、債権者(養育費を受け取るひと)1人、債務者(養育費の支払い義務があるひと)1人なので、4000円分の収入印紙が必要になります。
郵便切手
給料差し押さえをする場合、元夫の勤務する会社に取り立てをすることになるので、会社は第三債務者になります。
第三債務者が1人の場合、切手代は3000円程度です。
複数の場合には、それぞれに送付することになるので切手代が高くなります。
詳しくは申し立てる裁判所に確認すると良いでしょう。
送達証明書
送達証明書は、債務名義となる証書が公正証書か家庭裁判所での調停や裁判などで取得したものなのかによって費用が異なります。
公正証書の場合、公証役場にて手続きを行います。
費用は送達の申し立て1つにつき1400円、送達証明書で1枚250円かかります。
家庭裁判所での調停や裁判などでの債務名義を取得した場合には、送達証明書1枚につき150円かかります。
執行文付与
執行文付与は、裁判での和解調書や判決書、または公正証書で債務名義を取得した場合には申請が必要になります。
裁判での和解調書や判決書の場合には、家庭裁判所にて1枚につき300円で発行してもらえます。
公正証書の場合には、公証役場にて1枚あたり1700円で発行することができます。
なお家庭裁判所の場合、送達証明書と一緒に執行文の申請を行えば、400円で発行してもらえます。
第三債務者の資格証明書
元夫の給料や預貯金を差し押さえたい場合、第三債務者の資格証明書が必要です。
給料差し押さえの場合は、元夫が勤めている会社の登記簿を取得する必要があります。
預貯金の場合には、口座のある金融機関の登記簿が必要です。
窓口や郵送での請求の場合、1通につき600円かかります。
なお、オンラインで請求した場合には郵送だと1通500円、窓口受け取りだと480円と割安になります。
住民票、または戸籍謄本
あなたや元夫の住所が調停調書や公正証書などの債務名義となる証書に記載された住所と異なる場合には、現住所を証明する住民票や戸籍謄本が必要になります。
住民票や戸籍謄本は、1枚につき300円で取得することができます。
この他にも、元夫の保有している資産が分からない場合には、財産開示請求の手続きをしなければならないこともあります。
財産開示請求は1件につき2000円、切手代が3000円程度かかります。
財産開示請求でかかった費用は、最終的に元夫へ請求できますが、財産を取得するまではあなたが立替える必要があります。
 【養育費について考えよう】養育費の支払いは絶対?法的な拘束力はあるの?
【養育費について考えよう】養育費の支払いは絶対?法的な拘束力はあるの?
養育費の不払いで困ったなら弁護士への相談を検討してみよう
養育費の不払いは、離婚後の問題なので誰に相談すれば良いか分からない方もいらっしゃるかもしれません。
とはいえ黙って泣き寝入りしてしまうと、100万円単位で損してしまうことにもなりかねません。
養育費を受け取らなかったことで進学費用が捻出できず、子どもが希望していた学校に進学できなくなってしまうことも考えられます。
そのため、養育費が不払いになった場合にはまず弁護士への相談を検討してみてください。
といってもいきなり法律事務所に連絡するというのは、なかなかハードルが高いでしょう。
そんなときには役所などで定期的に開かれている弁護士の無料相談会への参加や、法テラスに相談することなどを検討してみてください。
 【離婚後の養育費】離婚後の養育費の取り決めを変更するにはどうすればいいの?
【離婚後の養育費】離婚後の養育費の取り決めを変更するにはどうすればいいの?
まとめ
今回は養育費が不払いになったときの対応について解説していきました。
養育費は親に支払う義務があり、また子どもにも受け取る権利がある重要なお金です。
しかし、残念ながら現状では法的に取り立てることのできる手段が非常に限られています。
また、手続きもかなり複雑で強制執行を考えても途中であきらめてしまう方もいらっしゃることでしょう。
こんなとき、弁護士に依頼すれば複雑な手続きを代理してくれます。
費用はかかりますが、今後のことを考えるとプラスになる可能性が高いのでお困りの際は一度弁護士に相談してみてください。
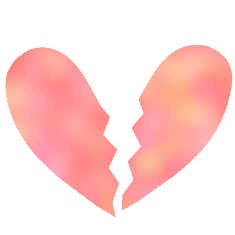 りこんの窓口
りこんの窓口



コメントを残す