この記事の情報提供者
離婚したいけど生活費の目処が立たないと悩んでいませんか?結婚生活においてもバリバリと働き、一人でも生きていける収入がない限り、経済的な不安はつきまといます。
離婚後の生活費、どうやってやりくりすればいいのかな……このお悩みの解決策に詳しいAnnalieseさんから、離婚に必要なチェックリストについて教えていただき、以下についてまとめました。
- 婚姻中の生活費(婚姻費用)とは?
- 離婚後、パートナーから生活費はもらえる?
- 離婚後、相手からもらえるお金
- 離婚後、生活費に困ったときに利用できる公的支援制度
- 離婚後に生活費で困窮しないようにするためのポイント
離婚後の生活費について頭を抱えている方は、ぜひご覧ください。
婚姻中の生活費(婚姻費用)とは?

まずは、「婚姻費用とは何なのか?」について、しっかりと確認しましょう。どういったときに問題となり得るのかもまとめましたので、あわせてご覧くださいね。
婚姻費用とは、結婚生活に必要なお金のこと
婚姻共同生活に必要な費用のことを「婚姻費用」といいます。婚姻費用の例としては、食費や被服費、住居費、水道光熱費、生活雑費、医療費などです。また、夫婦に子どもがいれば、子どもの生活費、教育医療費、習い事にかかる費用も婚姻費用となります。
「婚姻中の費用は基本的に夫婦で分け合わなければいけない」との決まりは、民法760条によって定められています。
婚姻費用が問題となるケース
夫婦の関係が円満であれば、こういった法律を知らなくても、婚姻費用を自然と分担できるケースが多いでしょう。問題となるのは、別居したときやどちらかが生活費を払わなくなったときが多いと考えられます。
 【弁護士監修!】別居後にもらえる婚姻費用とは?
【弁護士監修!】別居後にもらえる婚姻費用とは?
離婚後、パートナーから生活費はもらえる?

離婚後に経済的な苦境に立たされる人は、少なくありません。そのためパートナーから、「離婚後の生活費をもらえないかな…」と思う人は大勢います。
しかし、離婚すると婚姻費用として生活費をもらうことはできません。その理由は、婚姻費用が婚姻中に支払われる費用だからです。
つまり、婚姻が解消された離婚後には支払わなければいけないといった法律がありません。反対に婚姻中であれば、別居をしていても婚姻費用をもらえます。
 離婚するときは、必ず弁護士に相談した方が良いの?相談するべきタイミングとは?
離婚するときは、必ず弁護士に相談した方が良いの?相談するべきタイミングとは?
離婚後、相手からもらえるお金

離婚すると自分でお金を稼がないといけないので、軌道になるまで経済的に苦しむ可能性が…。そういったリスクを少しでも軽減できるよう、離婚後にパートナーからもらえるお金がないか、チェックしておきましょう。
慰謝料
たとえば夫の不倫やDVなどで離婚となった場合には、精神的苦痛があったとして慰謝料請求できる可能性があります。どれくらいの慰謝料がもらえるのかはケースバイケース。慰謝料の相場は、50万~300万円ほどといわれていますので、参考になさってください。
財産分与

財産分与とは、結婚後に夫婦で築き上げた財産を離婚に際して分け合うことです。たとえば、車や家(マンション)、貯金や家具などが財産分与の対象となるでしょう。こうした財産を、夫婦での話し合いや調停、裁判などによって分けることが財産分与といいます。
養育費
養育費とは、パートナーとの間に子どもがいるとき、離婚に際して子どもを引き取った側が相手から受け取れる養育費用のこと。子どもを育てるにはお金がかかるため、決まった費用を月々支払ってもらえるのです。
 【離婚したいけどお金が心配!】離婚前や離婚後のお金についてよくある疑問について①
【離婚したいけどお金が心配!】離婚前や離婚後のお金についてよくある疑問について①
 【離婚したいけどお金が心配!】離婚前や離婚後のお金についてよくある疑問について②
【離婚したいけどお金が心配!】離婚前や離婚後のお金についてよくある疑問について②
離婚後、生活費に困ったときに利用できる公的支援制度

離婚したあとの生活費に困ったときには、4種類の公的支援が受けられないか、確認することをおすすめします。公的支援制度はたくさんありますが、地域によって異なるため、確認することが大事。受けられる助成をしっかり把握すれば、お金に困るリスクを少なくできるので、詳しく見ていきましょう。
手当
経済的な支援制度における手当とは、以下のように自治体から助成してもらえる手当のことを指します。
- 児童扶養手当
- 児童手当
- 特別児童扶養手当
- 生活保護
- 就学援助など
これらのなかには、さかのぼって給付してもらえない手当もあるので注意が必要。もらえる手当をしっかりと受け取れるよう、時間に余裕をもって申請手続きを進めましょう。
貸付
手当ではなく一時的に自治体からお金を貸してもらうことで支援を受けられるケースもあります。貸付の面から見る経済的支援には、以下のような支援があるのでチェックしておきましょう。
- 母子福祉資金貸付金
- 生活福祉資金貸付制度
- 女性福祉資金貸付制度
- 応急小口資金など
たとえば東京都の母子福祉資金貸付金の場合、20歳未満の子ども等を扶養している母子家庭の母、または父子家庭の父などが対象となっています。こういった貸付制度を活用することで、離婚後の経済難を乗り切れる可能性が。
公的支援としての貸付なので、金利などの面で優遇されるケースが多いと考えられるので、有効活用しましょう。
生活

住居など、生活に関する支援も見逃せません。この支援には以下のようなものがあります。
- 母子生活支援施設の活用
- ひとり親家庭住宅助成制度
- 母子家庭等就業
- 自立支援センター事業
- ホームヘルパーの派遣など
これらを活用することで生活費を抑えられると期待できます。月々の出費をできる限り抑えることで、極度の貧困状態を免れることは多々あります。少しずつ貯金すれば、暮らしぶりを改善していくことも期待できるので、有効活用したいところです。
就職
就職に関する公的支援があることも要チェック。たとえば、東京都の母子家庭及び父子家庭自立支援給付金事業では、仕事に就くために教育訓練を受けた場合、原則としてかかった費用の6割に相当する金額が助成されることに。ほかにも就職に関する支援としては、以下のような支援があげられます。
- 母子家庭高等技能訓練促進費等給付金
- 寡婦等職業相談員への相談など
離婚後に生活費で困窮しないようにするためのポイント

離婚後、生活費に困らないためにも、支出と収入のバランスをとることをおすすめします。これからお伝えする3つのポイントをおさえて、離婚後の生活に備えましょう。
生活費を抑えられる家を探しておく
離婚後に引っ越す必要があるなら、新しい家を探しておくことが大切。できる限り家賃の安い物件をおさえておけば、生活費に困窮するリスクを少なくできます。
子どもがいる場合には、近くに保育園や小学校があるかどうかを確認しておくことも重要です。家賃を抑えることだけに気を取られていると、実際に生活をはじめたときに不便で暮らしていけない…」なんてことになりかねません。家賃を抑えるために駅から遠い物件を選んだのに、交通費が高額になってしまえば、逆効果になってしまうことも。
これらのことから、家賃と住みやすさのバランスを考え、新しい家を探しておきましょう。
就職先を見つけておく

もし、あなたが専業主婦やパートとして働いているのであれば、離婚する前にフルタイムで働ける就職先を見つけておくことが大事です。離婚してから新しい仕事を探しても、すぐに見つからないかもしれません。仕事が見つからないと、生活費が減る一方に。
こうなってしまうと精神的にも不安定になりやすくなるので、注意が必要です。
毎月の収入を把握する
もらえるお金や給付金のことを知っておけば、毎月の支出の目処を立てやすくなります。夫から慰謝料などをもらえるなら、きちんと手続きをしておきましょう。
また住む地域に支援があり、給付金としてもらえるのかを把握し、申請手続きを進めておくことも忘れてはいけません。もらえるものはすべてもらって、生活費の足しにしていきましょう。
まとめ
離婚後の生活費に困らないためには、収入と支出の管理を徹底しなければなりません。そのためにも、できる限り安定した仕事を探し、収入を確保しながら、賢く節約し、支出を抑えることが重要です。
ひとり親になることで、受けられる公的支援制度が出てくるかもしれません。そういったこともふまえて、できるかぎりもらえるお金を増やすよう、心がけましょう。この記事を参考に、離婚後の生活費に対する不安を少しでも軽くしてくださいね。
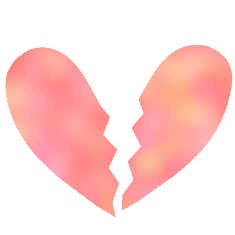 りこんの窓口
りこんの窓口



コメントを残す