離婚する夫婦のほとんどは離婚協議や離婚調停などの話し合いによって離婚を成立させます。
実際に2022年に厚生労働省から公表されたデータによると96.6パーセントの夫婦が協議または調停で離婚しています。
つまり離婚裁判はかなりのレアケースなのです。
今回は離婚裁判に至るまでの流れや実際の裁判の知識について解説していきたいと思います。
離婚裁判を行うには法律上の離婚事由が必要
夫婦仲が悪くなり離婚を切り出したのに、全然相手が応じてくれないと、「じゃあ裁判で決着付けよう!」といいたくなるひともいるかもしれません。
しかし、離婚裁判は、「裁判したいから」で簡単に起こせるものではありません。
通常の裁判は、話し合いでうまくいかなかったら地方裁判所に訴訟を申し立てることによって行うことができます。
しかし、離婚裁判の場合離婚協議で折り合いがつかなかったら、すぐに裁判へ移行できるわけではなく、その前に離婚調停を行い不成立になる必要があります。
というのも日本の司法は、家族のことはなるべく争いでなく話し合いで解決すべきという考え方があるからです。
また、離婚調停が不成立になったからといって必ず離婚裁判に移行できるわけではありません。
離婚裁判を行うには法律上で定められている離婚事由に当てはまる必要があります。
法律上で定められている離婚事由とは次の通りです。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上生死不明
- 配偶者が強度の精神病で回復が見込めない場合
- その他婚姻を継続し難い重大な事由
法律上の離婚事由のイメージとしてよく挙げられるのが、夫婦のどちらか一方が不貞行為や暴力などをふるい、被害者にあたる方が訴訟を申立てることを想像する方は多くいらっしゃるかと思います。
しかしながら、実際は必ずしも有責行為が絡んでくるわけではありません。
例えば親権を夫婦どちらも主張し、協議でも調停でも全く折り合いがつかない場合にも、法律上の離婚事由として認められるケースがあります。
親権の他にも長期間の別居なども法律上で定められている離婚事由にあたる可能性があります。
なお離婚を望んでいる方が有責配偶者の場合には、特別な事情をのぞき基本的に訴訟が認められないため注意が必要です。
離婚調停から離婚裁判までの流れ
離婚裁判を起こす前には、必ず離婚調停を起こす必要があります。
離婚調停とは基本的に相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立て、離婚の可否や財産分与、親権、養育費など離婚に関わるもののほとんどすべてを話し合うことができます。
なお、婚姻費用についても話し合いたい場合には、婚姻費用分担請求調停を別途申し立てる必要がありますが、話し合い自体は離婚調停と一緒にすることができます。
離婚調停は大体1か月から2か月に1回の頻度で行われます。
1度の調停で不成立になることは、相手が行方不明で調停を欠席する、罪を犯して服役中であるなどといったような特別なケースで、ほとんどは2回以上、多い方の場合には10回以上行います。
期間でいうと大体半年から1年くらいは調停をすることになります。
離婚調停では、夫婦の他に調停委員という役割のひとが仲裁役として当事者双方の話を聞き、妥協点を探っていきます。
調停委員は調停のリーダーである裁判官の手や足、目や耳となり動くので、悪い心証を抱かられると調停が不利なかたちで進む可能性があるので注意が必要です。
調停委員は夫婦の意見が折り合わずこのままではらちが明かない場合には調停を不成立にして裁判に移行するか打診することがあります。
当事者双方が調停を不成立にし、裁判に移行することに同意した場合には離婚調停が不成立になり、裁判へと進んでいきます。
なお、調停の場で相手が弁護士をつけていた場合、あなたから譲歩を得られるように「調停を不成立にして裁判で争いましょうか」と交渉してくることもあります。
弁護士は交渉術、法的知識において一般の方よりも長けているので自力で太刀打ちするのは非常に困難です。
そのため、相手が弁護士をつけていることが分かった場合には、話し合いが進む前にできるだけ早くあなたも弁護士に依頼した方がよいです。
というのも、何気なく発言した言動によって不利になる可能性が高いからです。
 【裁判離婚は簡単じゃない】裁判でシロクロはっきり離婚したいけどデメリットはあるの?
【裁判離婚は簡単じゃない】裁判でシロクロはっきり離婚したいけどデメリットはあるの?
離婚裁判の終わり方は判決だけじゃない
離婚調停が不成立に終わった場合、あなた、もしくは相手が離婚訴訟の申立てを行うことになります。
裁判は、訴訟を提起すれば後は裁判官がシロクロはっきり決めてくれ、即日判決が出るわけではありません。
裁判官は原告と被告の主張、また主張を裏付けるために提出された証拠や証人の証言をもとにどちらの主張が正しいのか判断し判決を下します。
どちらの主張に正当性があるのかは1度の裁判期日で判断するのではなく複数回裁判が開かれ判断されます。
そのため、最終的に判決が下るには平均して1年、長い場合には数年単位かかるケースもあります。
離婚裁判を行う場合、長期化すると夫婦関係が悪化し子どもの養育に影響がかかると予想されるため、裁判官は争いを終結させるため和解勧告を行うことがあります。
和解勧告は、裁判官が当事者同士に話し合いで解決できる余地があると判断したときに行うもので、双方が和解に応じる意思があった場合には法廷から別室に移り和解について話し合います。
それぞれ和解条件に折り合いがついた場合には、和解離婚が成立します。
また成立するケースは少ないですが、判決前に被告が原告側の主張をすべて受け入れた場合、認諾離婚が成立することもあります。
裁判は必ずしも判決によって結審するわけではなく、和解や認諾によって終結することもあるのです。
 離婚裁判の手続きを理解する!弁護士が教える訴訟の流れと対処法
離婚裁判の手続きを理解する!弁護士が教える訴訟の流れと対処法
 【裁判離婚は時間がかかる】離婚訴訟になった場合の3つの終結の仕方
【裁判離婚は時間がかかる】離婚訴訟になった場合の3つの終結の仕方
裁判は勝訴することがすべてではない
離婚裁判は勝訴すれば必ず有利な条件で離婚できるとは限りません。
勝訴して離婚が認められたり親権を取得することができたとしても、あなたが望む条件で財産分与や婚姻費用、慰謝料を得られないケースもあります。
離婚裁判で、離婚の可否だけ、親権の取得だけが争点ならば勝訴には大きな意味がありますが、財産分与や慰謝料などの金銭に関わることも争点とした場合、あなたの主張が全面的に認められる全面勝訴は難しいといえます。
更にいえば、離婚裁判で不貞行為などの慰謝料を争った場合、大体100万円から300万円が相場です。
慰謝料請求額を1000万円以上と高額に設定したとしても、請求額通りの判決になることはかなりレアケースです。
一方で、有責配偶者の方の場合、裁判に敗訴したとしても慰謝料の請求額が相手方の請求額を大幅に下回ったり、あなたが想定していた支払額よりも低い場合、裁判に負けたとはいえ実質勝訴といっていいこともあります。
このように裁判は勝訴したからといって、必ずあなたの利益になるとは限りません。
裁判になった場合金銭的にも時間的にも精神的にも大きな負担があなたにかかると予想されます。
そのため頭から「裁判で決着をつける」と考えるのではなく、本当に裁判でしか決着をつけることができないのか、裁判を行うメリットがあるのかなど冷静になって考える必要があります。
 【親権問題】親権は女性が絶対有利?争いになったら調停や訴訟を回避するには?
【親権問題】親権は女性が絶対有利?争いになったら調停や訴訟を回避するには?
まとめ
今回は離婚裁判の流れや知識について解説していきました。
はっきりいうと、離婚裁判はあなたにさまざまな負担がかかるため、本当にやむを得ない状況にならない限り、回避した方が良いです。
勝訴すれば、すっきり離婚できると考える方もいらっしゃるかもしれませんが、判決内容によってはもやもやが残ることもあります。
また離婚裁判に発展した場合、高度な法知識が必要となるため弁護士の力が必要不可欠といっても過言ではありません。
争いが長引くほど裁判にかかる費用が高くなり、離婚成立までに時間を要する可能性が高くなるので、まずは裁判や調停などの前段階で弁護士に相談することを検討してみてください。
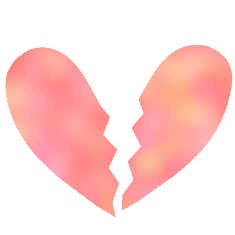 りこんの窓口
りこんの窓口



コメントを残す